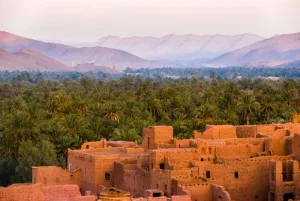教育制度の特徴
カンボジアの教育は、6・3・3制といって、小学校6年、中学校3年、高校3年です。6歳から学校に通いはじめます。公立の学校は無料で通えますが、すべての子どもが行けるわけではありません。特に農村部では、家の手伝いをしなければならなかったり、学校が近くになかったりして通えない子もいます。
教育方法
カンボジアの学校では、先生が黒板を使って教える「板書式の授業」が多く行われています。でも最近では、子どもたちが自分で考えたり、話し合ったりするアクティブラーニングも取り入れられてきています。英語やパソコンの授業も少しずつ増えてきて、未来に向けた教育が始まっています。
教育への取り組みや支援
カンボジアは、長い戦争のあと、教育がほとんどなくなってしまった時期がありました。今では国や国際機関、NGOなどが協力して、学校を建てたり、先生を育てたりする支援が行われています。日本もその支援をしていて、カンボジアにたくさんの学校を建てるお手伝いをしています。
子供達の1日の過ごし方
カンボジアの小学校は午前と午後の二部制が多く、子どもたちはどちらかの時間に通学します。たとえば午前に学校へ行く子は、午後は家の手伝いや畑仕事をすることもあります。家で宿題をする時間が取れない子もいるので、学校での学びがとても大切です。遊びの時間は少なめですが、友達と一緒に過ごすのはどこの国でも楽しい時間ですね。
教育と社会の関係
カンボジアでは、教育が「貧しさをなくすカギ」と考えられています。学校に通って知識を身につけることで、よりよい仕事につき、生活を安定させることができます。また、読み書きができることで、選挙で自分の意見を表したり、健康に関する情報を得たりと、社会に参加する力にもつながります。
国が抱える教育の課題と未来
カンボジアでは、まだ先生の数が足りなかったり、教科書が古かったりするという課題があります。特に農村部では、子どもたちが学校を途中でやめてしまうこともあります。ですが、国の経済が成長してきたことや、国際的な協力が続いていることで、少しずつ明るい未来が見えはじめています。 今後は、もっと多くの子どもが、夢に向かって学べるようになることが期待されています。
教育と文化や価値観の関係
「感謝」と「敬意」を大切にする文化
カンボジアでは、先生はとても尊敬される存在です。
学校では、朝のあいさつや礼儀作法をしっかり学び、「目上の人を大切にする」という考え方が育まれています。
これは、仏教の教えとも深くつながっており、家族や年上の人を敬う文化のもとになっています。
「共に助け合う」精神の育成
教育支援の多くは、地域の力を合わせて行われることが多く、教室を作るために村の人たちが自ら木材を運んだり、家族が寄付をしたりすることもあります。
この経験が、「みんなで支え合って生きる」という価値観を子どもたちに自然と教えているのです。
「自然とともに生きる」知恵
カンボジアの農村部では、学校の外でも学びがあると考えられています。たとえば、稲作や川の管理など、自然と共に生きる知恵を親や地域の人から学ぶことが多いです。
これは、カンボジアの人たちが「自然を大切にする心」を育むもととなっており、現代の持続可能な暮らしにもつながっています。
「宗教」と「道徳」が身近な学び
カンボジアの多くの学校では、仏教に基づいた道徳教育も取り入れられています。
たとえば、「うそをつかない」「人を傷つけない」といった基本的な考え方は、授業の中でも繰り返し伝えられ、正直さや思いやりを大切にする人になるよう導かれています。
まとめ
カンボジアでは、教育を受けることが未来の希望につながっています。戦争でいったん失われた教育を、もう一度みんなで力を合わせて立て直しているところです。たくさんの人の助けと、子どもたちの努力が、カンボジアの新しい社会をつくっていきます。日本とはちがうけれど、大切にしていることは同じ。「学びたい」という気持ちは、どこにいてもきらきらしていますね。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい