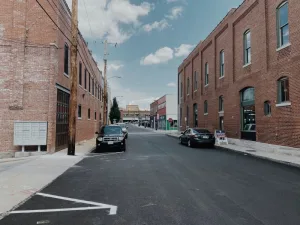教育制度の特徴
モルドバの教育制度は、「4-5-3制」が一般的です。これは、小学校(4年間)、中学校(5年間)、高等学校(3年間)という構成を指します。このうち、小学校と中学校の9年間が義務教育とされています。
また、モルドバは2005年からヨーロッパの高等教育制度の標準化を目指す「ボローニャ・プロセス」に参加しています。これにより、大学進学には高校卒業後に「バカロレア」と呼ばれる国家統一試験の合格が必要となります。これは、ヨーロッパの他の国々と同じように、学歴が国際的に通用するようにするための重要な取り組みです。
公用語はルーマニア語ですが、国内にはロシア語を話す人々も多いため、学校によってはロシア語での授業が行われることもあります。外国語教育にも力を入れており、小学校2年生から第一外国語を学び始め、中学校からは第二外国語の学習も始まります。
教育方法
モルドバの教育は、知識を詰め込むだけでなく、子どもたちの「市民性」を育むことに重点を置き始めています。
特に注目すべきは、近年の教育改革で導入された**「社会のための教育」**という科目です。この科目では、生徒たちがただ教科書を学ぶだけでなく、実際に議会を見学したり、法律や社会の仕組みについて議論したりします。成績ではなく、能力や成長に焦点を当てた評価が行われることもあり、生徒たちに人気があると言われています。
また、ウクライナからの避難民の子どもたちを受け入れる中で、オンライン授業や語学講座など、ICT(情報通信技術)を活用した新しい教育方法も導入されています。これは、様々な背景を持つ子どもたちが学び続けられるようにするための、柔軟な取り組みと言えるでしょう。
教育への取り組みや支援
- ウクライナからの避難民支援 ウクライナ危機を受け、モルドバに避難してきた子どもたちが学びを続けられるよう、オンライン授業のための教室の開設や、学習教材の提供が行われています。
- 国際NGOの活動 日本のNGO団体も、貧困家庭の子どもたちを対象にした「デイケアセンター」の運営を支援しています。ここでは、放課後の学習支援や食事の提供、心のケアなどが行われ、子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供しています。
- 日本政府からの支援 日本政府は、ユニセフなどを通じて、学校での水・衛生サービスの提供や、障害を持つ子どもたちの早期支援システムの強化を支援しています。
こうした支援は、国全体の教育レベルを底上げするだけでなく、すべての子どもたちが等しく教育を受けられる機会をつくるために、大きな役割を果たしています。
子供達の1日の過ごし方
一般的なモルドバの小学生は、朝、学校へ登校し、午前中から午後の早い時間にかけて授業を受けます。授業は通常、ルーマニア語(またはロシア語)で行われ、数学、歴史、地理、理科などの科目を学びます。
放課後は、日本の学童保育に似たデイケアセンターに通う子どもたちもいます。ここでは、宿題をしたり、絵を描いたり、歌やダンスを楽しんだりして過ごします。経済的な理由で親が出稼ぎに行っている家庭の子どもたちにとっては、安全で温かい居場所となっています。
夕方以降は、家族と一緒に過ごしたり、習い事に通ったりします。日本と同じように、スポーツや芸術活動に取り組む子どもたちも少なくありません。
教育と社会の関係
モルドバの教育は、国の未来を担う人材を育てるための重要な基盤と位置付けられています。しかし、経済的な問題や社会の変化が、教育に大きな影響を与えています。
特に、多くの親が出稼ぎのために国外へ移住する「家族の分断」は、子どもたちの心に大きな負担をかけています。このような状況下で、学校や支援団体は、子どもたちが孤立しないよう、心のケアや安定した学習環境の提供に力を入れています。
一方で、モルドバの若者たちは、EU加盟を目指す国の変化に大きな期待を寄せています。彼らは、より良い未来のために、政治や社会問題に関心をもち、積極的に発言するようになっています。教育は、彼らがグローバルな視点を持ち、社会の変革を担う力を育む場所となっています。
国が抱える教育の課題と未来
- 教育の質の格差 首都キシナウの学校は近代的な設備が整っている一方、地方の村では設備や教員の不足が課題となっています。これにより、子どもたちの学習環境に大きな格差が生じています。
- 貧困による影響 貧しい家庭の子どもたちは、教材が買えなかったり、十分な食事が取れなかったりするため、学業に専念することが難しい状況にあります。
- 教員の待遇改善 教員の給与が低いため、優秀な人材が教育現場に留まらず、海外へ流出してしまう問題もあります。
これらの課題を解決するため、モルドバ政府は国際機関やNGOと連携し、教育システムの改善に取り組んでいます。
未来に向けては、教育のデジタル化を進めたり、市民教育をさらに充実させたりすることで、すべての子どもたちが質の高い教育を受け、社会の変化に対応できる力を身につけられるような教育体制を目指しています。
教育と文化や価値観の関係
家族を大切にする価値観
多くのモルドバ人が出稼ぎで国外に暮らす現状は、家族の絆をより一層強いものにしています。子どもたちは、祖父母や親戚に育てられることが多く、学校でも家族の重要性や故郷を愛する心が教えられます。
この価値観は、モルドバの**「家族の食卓を囲む文化」**に現れています。海外で働く親が一時帰国すると、親戚一同が集まり、手作りの料理を囲んで語り合います。この時、親が海外で学んだ新しい知識や文化が家庭に持ち込まれ、子どもたちの視野を広げる機会にもなります。
ワインに象徴される「故郷への愛着」
モルドバは世界有数のワイン生産国であり、その歴史は数千年前にも遡ると言われています。このワイン文化は単なる産業ではなく、モルドバ人のアイデンティティそのものです。学校の授業や社会教育では、故郷の歴史や文化、特にワイン造りの伝統が大切に教えられます。子どもたちは、ブドウ畑の手入れを手伝ったり、収穫祭に参加したりする中で、自然と故郷の土地や文化に誇りを持つようになります。
この教育は、たとえ将来海外へ移住したとしても、故郷のワインを友人や家族に振る舞い、モルドバの文化を伝えるという行動に繋がります。ワインは、離れて暮らす人々を結びつけ、故郷への愛着を再確認するシンボルとなっているのです。これらの価値観は、モルドバの若者たちが、伝統を大切にしながらも、グローバルな視点を持ち、社会を変革しようとする力強い原動力となっています。
まとめ
モルドバの教育は、経済的な困難や社会的な課題に直面しながらも、未来を担う子どもたちのために着実に進化を遂げています。特に、新しい教育科目の導入や、国際的な支援の受け入れは、子どもたちが世界に目を向け、より良い社会を自ら築いていくための力を育んでいます。この自由研究を通して、遠い国モルドバの教育事情を知ることで、改めて日本の教育や、世界の子どもたちの学びについて考えるきっかけになったのではないでしょうか。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい