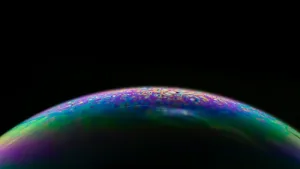INDEX
野生動物と共に生きる!動物たちを守る方法を考えてみよう!
私たちの住む地球には、力強く大地を駆けるゾウや、しなやかに木々を渡るサル、美しい声でさえずる鳥たちなど、数えきれないほどの野生動物が暮らしています。彼らは、地球という大きな家族の大切な一員です。しかし今、人間の活動によって彼らの住処が奪われたり、地球環境が変化したりして、多くの動物たちが絶滅の危機に瀕しています。
この研究では、なぜ野生動物を守る必要があるのか、その理由を深く探ります。そして、彼らと共に未来も生きていくために、私たち一人ひとりに何ができるのかを考え、行動するための冒険に出かけましょう。
野生動物を守ることは、単に「動物がかわいそうだから」という理由だけではありません。それは、私たち自身の未来を守ることにも繋がる、とても大切な学びなのです。
- 彼らは「生態系」のバランサー 野生動物は、自然界の絶妙なバランスを保つ重要な役割を担っています。例えば、オオカミのような肉食動物は、シカなど草食動物が増えすぎるのを防ぎ、森の植物が食べ尽くされるのを守ります。ミツバチは植物の花粉を運び、私たちが食べる野菜や果物が実るのを助けます。一つの種がいなくなると、その影響はドミノ倒しのように広がり、自然全体のバランスが崩れてしまうのです。
- 彼らは地球からの「贈り物」 動物たちのユニークな姿や生き方は、私たちに驚きや感動、癒やしを与えてくれます。また、豊かな生物の多様性は、新しい薬や技術開発のヒントが隠された「未来の宝箱」でもあります。この宝箱を失うことは、人類にとって計り知れない損失となるのです。
- 未来の世代への「責任」 今、私たちの行動が、未来の子供たちが図鑑でしか見られない動物を増やすか、それとも本物の動物たちに出会える世界を残せるかを決めます。この豊かで美しい生命のつながりを、次の世代にしっかりと手渡していくことは、今を生きる私たちの大きな責任です。
自由研究のゴール
- 初級ゴール 【知る・伝える】絶滅危惧種新聞をつくろう! 君が好きな野生動物や、日本の絶滅危惧種(例:ツシマヤマネコ、ライチョウ)を一種選び、その動物の生態、なぜ数が減っているのか、どんな保護活動が行われているのかを調べよう。そして、調べたことをイラストや写真と共に「動物保護新聞」や「生態カード」にまとめて、みんなに伝えよう!
- 中級ゴール 【調査・分析する】地域の動物と人間の共存マップをつくろう! 君の町に住む野生動物(タヌキ、イノシシ、ハクビシンなど)と人間の関わりを調査しよう。動物がよく現れる場所や、農作物の被害、交通事故が起きやすい場所などを地図にまとめます。さらに、地域で行われている共存の工夫(動物注意の看板、ゴミ箱の管理など)を分析し、レポートにまとめよう。
- 上級ゴール 【行動・提案する】動物保護のプロに学び、アクションを起こそう! 動物園や水族館、地域の動物保護団体(NPO)などに連絡を取り、活動内容についてインタビューをしてみよう。そして、専門家から学んだことをヒントに、自分たちの学校や地域でできる保護アクション(野生動物のための募金活動、外来種駆除イベントの企画、啓発ポスターの作成など)を提案し、実行に移してみよう。
動物たちを守るための様々な戦いや挑戦をしている事例
世界や日本では、動物たちを守るための様々な戦いや挑戦が行われています。
- コウノトリ、再び大空へ(兵庫県豊岡市) かつて農薬などの影響で、一度は日本の空から姿を消したコウノトリ。しかし、地域の人々が協力し、コウノトリの餌となるドジョウやカエルがすめるように「農薬を使わない米作り」を広げました。その結果、豊かな自然が蘇り、コウノトリが再び野生で暮らせるようになった、感動的な成功例です。
- ツキノワグマとの棲み分け(長野県軽井沢町) 森の食べ物が減り、人里に出てきてしまうツキノワグマ。すぐに捕まえて殺処分するのではなく、軽井沢町では特別な対策をしています。クマが絶対に開けられないゴミ箱を設置したり、専門家が犬を使って「ここは人間のエリアだよ」と根気強く教えたりすることで、人とクマが適切な距離を保って共存する道を探っています。
- チョコレートでオランウータンを救う?(ボルネオ島) オランウータンの住処である熱帯雨林が、お菓子や洗剤の原料となる「パーム油」を採るための農園開発によって、急速に失われています。しかし、私たちにもできることがあります。環境に配慮して作られたことを示す「認証マーク」のついた商品を選ぶこと。その小さな選択が、遠い国の森と動物を守ることにつながります。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- テーマを自分ごとに引き寄せる 「野生動物」と大きく構えず、「通学路で見かける鳥の観察」「近くの川の外来種調査」「海洋プラスチックごみとウミガメの関係」など、身近で具体的なテーマに絞ると、より深く、面白く探求できます。
- 安全第一!フィールドワークの心得 山や川へ調査に行く際は、必ず大人と一緒に行きましょう。ハチやヘビ、クマなどの危険な生き物もいるので、服装や持ち物をしっかり準備し、もしもの時の対応を学んでおくことが大切です。動物を見つけても、驚かせないようにそっと観察し、絶対に触ったり餌をあげたりしないでください。
- 多角的な視点を持つ 農作物を荒らす「害獣」と呼ばれる動物たち。でも、なぜ彼らは人里に出てくるのでしょうか?彼らの視点に立てば、元々の住処である森が減って食べ物がなくなったのかもしれません。動物の保護と、人々の生活。両方の立場から物事を考えることで、問題の本当の根っこが見えてきます。
- プロに話を聞きに行こう! 図鑑やネットの情報だけでなく、動物園の飼育員さんや水族館のトレーナーさん、地域の博物館の学芸員さんに話を聞いてみましょう。「種の保存」のためにどんな工夫をしているのか、現場のプロの話は、何よりの学びと発見に満ちています。
自由研究の進め方
ステップ1 計画(Plan)
- テーマ決め どの動物や問題について調べたいか、はっきりさせる。
- 問いを立てる 「なぜこの動物は減っているの?」「どうすれば一緒に暮らせる?」など、研究で明らかにしたい「問い」を決める。
- 調査計画 本やネット、現地調査、インタビューなど、どうやって調べるか具体的な計画とスケジュールを立てる。
ステップ2 実行(Do)
- 情報収集 計画に沿って、本やウェブサイトで生態や現状を調べる。
- 調査・観察 現地でフィールドサイン(足跡やフンなど)を探したり、目撃情報を集めたりする。
- インタビュー 動物園や市役所など、専門家にアポイントを取って話を聞く。
ステップ3 評価(Check)
- 情報整理 集めた情報を、地図やグラフ、年表などを使って分かりやすく整理する。
- 考察 立てた「問い」に対して、自分なりの答えを考える。「なぜそうなったのか?」という原因を深く掘り下げる。
ステップ4 改善・発表(Action)
- まとめ 研究の動機から、方法、結果、考察、そして「私たちにできること」の提案までを、模造紙やスライドにまとめる。
- 発表 君の発見と提案を、家族や友達、クラスのみんなに自信を持って伝えよう!
自由研究から発見したアイデア
研究から生まれた、世界をちょっと良くする新しいアイデアを形にしてみよう!
- ミニチュア「動物の道(アニマルパスウェイ)」の制作・提案 道路によって森が分断され、交通事故にあう動物は少なくありません。彼らが安全に道路を横断できる「動物の道」の必要性を訴えるため、そのミニチュア模型を制作し、どうして必要かをまとめた手紙と一緒に、市役所や道路会社に提案してみよう。
- 野生動物との「共存グッズ」を開発! 身近な材料を使って、動物とのトラブルを平和的に解決するグッズを考えてみよう。例えば、カラスが嫌がる光を反射するモビールや、イノシシが苦手なハーブを植えたプランターなど。その効果を観察・記録して発表しよう。
- 地域の動物保護PRキャラクターを誕生させよう! 地域の絶滅危惧種や、身近な野生動物をモチーフにした、可愛くて親しみやすいPRキャラクターをデザインしよう。そのキャラクターが主人公の4コマ漫画やSNSアカウントを作って、動物の生態や保護の必要性を楽しく発信する活動です。
この自由研究に関連する仕事
- 動物園・水族館の飼育員 動物たちの一番近くで健康を管理し、種の保存のための繁殖計画などを担当する、命のスペシャリスト。
- 野生動物専門の獣医師 交通事故にあったり、病気になったりした野生動物を治療し、再び自然に返す手助けをする、動物のお医者さん。
- レンジャー(自然保護官) 国立公園などをパトロールし、密猟を防いだり、動物の数を調査したりする、自然環境の守り人。
- 動物生態学者 動物の行動や習性を詳しく研究し、科学的なデータに基づいて効果的な保護方法を考える、動物博士。
- インタープリター(自然解説員) 自然公園や森で、動物たちの生態や自然の面白さを人々に分かりやすく伝える、自然と人との架け橋。
まとめ
野生動物たちは、言葉を話すことはできません。しかし、その生き様や、時に見せる必死な姿は、私たちに多くのことを語りかけています。彼らは地球という大きな生命の輪を支える、かけがえのない仲間です。
この自由研究は、彼らの声なき声に耳を澄まし、「かわいそう」という気持ちを一歩進めて、「どうすれば共に生きられるか」という知恵と行動に変えるための旅です。身の回りの小さな命に目を向け、そのつながりの大切さを知ること。その発見が、豊かな地球の未来を創る、君の大きな力になります。さあ、一緒に新しい一歩を踏み出しましょう!
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。