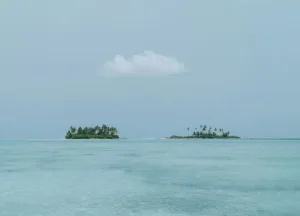教育制度の特徴
赤道ギニアの教育は、教育科学省(MEC)が管轄し、幼稚園、初等教育(1~6年)、中等教育(基礎4年+バチェラート2年)、高等教育という4段階で構成されています。幼稚園と初等教育は6歳から14歳まで義務・無償と定められ、国民の基本的教育権が法律で保障されています。しかし教育成果は西・中央アフリカ諸国に比べ遅れをとっており、2015年時点の15歳以上識字率は95.3%と高水準ながら、純就学率は幼児42%、初等60~86%、中等43.6%にとどまります。施設不足や教員の質、児童の栄養状態も課題です
引用元 Wikipedia
教育方法
教育課程は国家カリキュラムに基づく教科書中心型で、授業は主に講義形式(teacher-dominated)で進められます。幼稚園では遊びや創造活動を通じた学びが導入されている一方、初等・中等では教員主導の板書・暗記学習が中心で、対話型・主体的学習は限定的です。また、2007年教育法により「遠隔教育(Distance Education)」が正式認められ、スペイン国立遠隔教育大学(UNED)や民間ITCプロジェクトによるコンピュータラボ運営などICT活用の試みもありますが、全国的な普及には至っていません
引用元 World BankWikipedia
教育への取り組みや支援
政府は国家開発計画の一環として「Programa Mayor Educación Para Todos」やPRODEGE(Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial)を推進し、幼稚園・初等の普及、中等就学率98%を目標に掲げています。資金は大統領府、Trident Energy、Kosmos Energyなどが提供し、UNESCO・UNICEF・世界銀行による技術支援、スペイン・フランスの協力でICTラボ整備、国費留学(過去40年で50万人超)など多方面からサポートが行われています
引用元 World Bankオープンナレッジバンク
子供達の1日の過ごし方
年間約180~200日、計900時間前後(1日あたり約5時間)の授業が行われ、多くの学校は午前7時半ごろ開始、午後12時半前後に終了します。校内給食制度は整備されておらず、子供たちは家庭から弁当を持参するか、校外売店で軽食を購入します。授業後は農作業や家事、路上販売などで家族を支援するケースが多く、学習環境や宿題に充てる時間が限られることも少なくありません
引用元 unesdoc.unesco.orgFAOHomeeveryculture.com
教育と社会の関係
教育は社会的移動や経済発展の鍵である一方、教育科学省の予算配分はわずか2~3%でサブサハラ平均16%を大きく下回り、公共・私立、都市・農村、富裕層・貧困層間の格差を助長しています。また、教員の専門性不足や教材・施設の不足が学力差を生み、社会的不平等が固定化する要因となっています
引用元 WikipediaWikipedia
国が抱える教育の課題と未来
現在の主な課題は、①児童の高い離学・繰り返し率、②教員養成・登用の不十分、③ICT・教材・施設の整備不足、④ジェンダーや地域間格差の是正、⑤教育財政の脆弱性です。今後は、全国的なEMIS(教育統計情報システム)の強化、遠隔・デジタル教育の普及、PPPによる私立教育の質担保、子供中心型(Child-Centered)教育への転換、現金給付やスクール・グランツを通じたドロップアウト防止などが期待されています
引用元 World BankWorld Bank
教育と文化や価値観の関係
年長者への敬意の醸成
赤道ギニアの学校教育では、「年長者を敬う」ことが重要な価値観として教えられます。家庭や地域社会でも尊重されるこの風習が、教室でも板書や口頭指導を通じて子どもたちに継承されています 引用元 エブリーカルチャー。
バイリンガル教育による言語アイデンティティの強化
公用語のスペイン語と、最大多数を占めるファング語など現地語を併用する授業が行われ、母語文化への誇りを育てています。これにより、急速なグローバル化の中でも自国の言語・文化を守る意識が根付いています
引用元 Wikipedia。
伝統音楽・語り部文化の授業への組み込み
美術・音楽の時間にファングの大太鼓や木琴(シロフォン)、語り部(ストーリーテラー)の技法を学ぶカリキュラムがあり、伝統芸能を子ども時代から体験的に理解する機会が提供されています 引用元 Encyclopedia Britannica。
イニシエーション儀礼の言語・習慣教育
地域社会で行われる成人の通過儀礼や結婚式の言語表現を、学校の社会科や民俗学の授業で取り上げ、若い世代が自分たちのルーツを学び、伝統行事を後世へつなげる役割を果たしています 引用元 メキシコ歴史博物館。
キリスト教カトリック校で培われる共同体意識
就学率の向上に伴い多くの子どもが通うカトリック系学校では、チャリティや奉仕活動をカリキュラムに組み込み、互いに助け合う「連帯」の精神が根付いています 引用元 Wikipedia。
まとめ
赤道ギニアの教育は、法的には幼稚園から初等教育まで無償・義務化され、高い識字率を誇りますが、就学率の低迷や教員・施設の不足、財政制約、地域格差など多くの課題を抱えています。国家開発計画や国際協力による改革が進む中、実効性のあるデータ基盤と学習環境の整備、子供一人ひとりのニーズを重視した教育改革が、持続可能な発展と公平な社会実現の鍵となるでしょう。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい