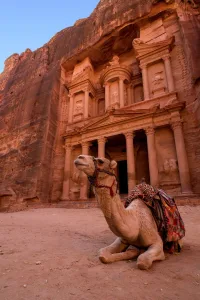教育制度の特徴
コンゴ民主共和国では、基本的に小学校6年、中学校2年、高校4年の制度がとられています。6歳からの小学校は「義務教育」とされていて、学校に通うことが国のルールになっています。最近では、初等教育の無償化(無料化)が進められ、少しずつ多くの子どもたちが学校に行けるようになってきました。
教育方法
授業では黒板とチョークを使った伝統的なスタイルが多く、教科書を読む、先生の話を聞く、ノートを書くという流れが基本です。ただし、教科書が足りない学校も多く、グループで1冊を使うこともあります。最近では、絵や音楽、ゲームなどを取り入れた授業を行う先生も出てきて、少しずつ新しい学びの方法が増えてきています。
教育への取り組みや支援
国の力だけでは足りないため、世界中のNGO(非政府組織)や国際機関(ユニセフやユネスコなど)が学校の建設や教材の支援をしています。また、女の子の教育を特に大事にする取り組みも増えています。これは、「女の子が教育を受ければ、将来、家庭や地域ももっと良くなる」と考えられているからです。
子供達の1日の過ごし方
都市部の子どもたちは朝から制服を着て登校し、昼過ぎには家に帰ります。
一方、地方の子どもたちは朝早くから水くみや農作業の手伝いをしてから学校へ行くこともあります。通学に1時間以上かかる子も多く、裸足で山道を歩く子どもたちもいます。それでも学校に行くことを楽しみにしている子がたくさんいます。
教育と社会の関係
教育は、コンゴの未来をつくる大切な鍵です。学校に通って文字が読めるようになると、病気の予防や政治への関心も高まり、生活が大きく変わることがあります。教育を受けた子どもたちは、大人になって医師や先生、技術者となり、自分の国を良くしていく力になります。
国が抱える教育の課題と未来
コンゴでは、長年の内戦や貧困の影響で、まだ学校に通えない子どもがたくさんいます。また、先生の数も足りず、教室が足りない学校もあります。ですが今、国の中でも「教育こそが希望」という考えが広がっており、未来のために学校を増やしたり、新しい先生を育てたりする動きが進んでいます。
教育と文化や価値観の関係
家族や地域との強い「つながり」を大切にする心
コンゴでは、教育が十分でない時代から「家族や村で助け合う」ことがとても大切にされてきました。今でも学校では「助け合い」や「年下の子を守る」ことを教える場面があり、コミュニティ(地域)の絆を大事にする文化が育まれています。
口頭文化(話し言葉で伝える知恵)を大切にする
学校で本が不足していることが多いため、先生が語り伝える教育が主流です。そのため、人の話をよく聞く力や、話すことで学ぶ習慣が発達しています。この文化は、昔話や物語を語り継ぐ「グリオ(語り部)」の伝統にもつながり、今でも子どもたちが大人の話を真剣に聞いて学ぶ風土があります。
音楽とダンスが学びや表現の手段に
コンゴの教育現場では、読み書きだけでなくリズムや歌で覚える授業も行われます。これは、伝統音楽やダンスが生活に深く根づいているためです。教育の中で文化芸術が自然に組み込まれているのが特徴で、音で学び、体で感じる学び方が子どもたちの創造性を育てています。
自然や土地への敬意が深まる教育
地方の学校では、教室が外にあることも多く、自然の中での学びが日常です。農業や動物、天候についての知識を生活の中で学ぶため、自然を大切にする価値観が育ちます。「自然は先生」という感覚は、コンゴならではの文化的背景につながっています。
まとめ
コンゴ民主共和国の教育は、まだ課題も多いけれど、それ以上に「学びたい」という子どもたちの気持ちがあふれています。学校へ行くことが当たり前ではない場所だからこそ、学ぶことの意味がとても大きいのです。この国の教育を知ることで、私たちが当たり前だと思っていることのありがたさにも気づけるはずです。そして、世界のどこかで同じように学んでいる仲間の存在に、やさしいまなざしを向けられるようになりますように。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい