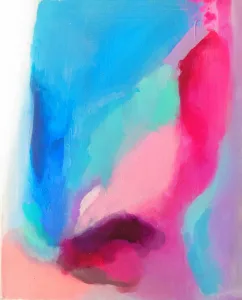今回のテーマ
「家庭で採取できるサンプルを顕微鏡で観察する方法を考える」
この研究のテーマは、私たちの生活の中から「マイクロプラスチック」を探し出すことです。マイクロプラスチックとは、大きさが5mm以下のとても小さなプラスチックの粒のこと。ペットボトルやレジ袋などが紫外線や波の力で細かく砕かれてでき、世界中の海や川、そして水道水や食塩の中からさえも見つかっています。今回は、特別な研究室ではなく、お家にあるものや、簡単に手に入る道具を使って、この小さな脅威を観察する方法を考えていきます。
自由研究の目的
なぜ、目に見えないほど小さなプラスチックを学ぶ必要があるのでしょうか?それは、マイクロプラスチックが地球全体の環境や、生き物、そして私たち人間の健康にも影響を与える可能性があるからです。小さな魚がマイクロプラスチックを食べ、その魚を大きな魚が食べ…というように、食物連鎖を通じて私たちの食卓にものぼってきています。この問題を学ぶことで、普段使っているプラスチック製品がどこへ行くのかを想像する力がつき、科学的な視点で物事を調べる探究心も育ちます。地球の未来を考える、大切な一歩になるのです。
自由研究のゴール
- レベル1 見つける!
まずは、家庭にあるサンプル(食塩や水道水など)から、マイクロプラスチックと思われるものを顕微鏡で「見つける」ことを目指そう! - レベル2 比べる!
違う種類の食塩(海の塩、岩塩など)や、違う場所の砂(公園、砂浜など)を比べてみよう。どこに多く含まれているかな?形や色に違いはあるかな? - レベル3 分析する!
見つけたものが本当にプラスチックなのかを考えてみよう。熱した針を近づけるとどうなるか(※必ずお家の人と安全に注意して行いましょう)、光に透かすとどう見えるかなど、簡単な分析に挑戦してみよう。
マイクロプラスチックを発見の事例
世界中の研究者が、いろいろなものからマイクロプラスチックを発見しています。君の自由研究のヒントになるかもしれない事例を見てみましょう。
- 食塩の中から発見!
ある研究では、世界各国で売られている食塩を調べたところ、多くの製品からマイクロプラスチックが見つかりました。特に、海水を原料とする塩から多く見つかる傾向があったそうです。 - 水道水やペットボトルの水からも!
私たちが毎日飲む水からも、マイクロプラスチックは検出されています。浄水場できれいにしているはずの水道水にも、ごく微量ですが含まれていることがあるのです。 - 洗濯で出る「繊維くず」
フリースなどの化学繊維でできた服を洗濯すると、目に見えない細かい繊維が抜け落ち、それがマイクロプラスチックとして川や海に流れ出ています。洗濯機の排水を少しだけ採取して観察すると、たくさんの繊維が見つかるかもしれません。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- 「混入(コンタミネーション)」を防ごう!
調査中に、空気中のホコリや自分の服の繊維が入ってしまうと、それがマイクロプラスチックなのか、元からサンプルに入っていたものなのか区別がつきません。観察する時は、できるだけホコリの少ない場所で、綿の服を着て、手をよく洗ってから行いましょう。 - 記録をきちんと取ろう!
「いつ」「どこで」採取したサンプルか、どんな手順で観察したか、そして何が見えたかを、写真やスケッチで詳しく記録しましょう。スマートフォンの顕微鏡なら、写真撮影も簡単です。 - 安全第一!
顕微鏡の操作や、もし熱を使った実験をする場合は、必ずお家の人と一緒に行いましょう。薬品は使わず、安全な方法で観察することが大切です。
自由研究の進め方
用意するもの
- 顕微鏡 スマートフォンに取り付けるタイプの安価なものでOK(100倍程度見えると良い)
- 調べたいサンプル 食塩、砂糖、砂、洗濯機の排水など
- 観察用の容器 シャーレ(ペトリ皿)や、ガラスの小皿
- 道具 スポイト、ピンセット、ろ紙(コーヒーフィルターでも可)、ビーカー(ガラスのコップでも可)
- 記録用具 ノート、ペン、スマートフォン(写真撮影用)
手順
- 仮説を立てる 「海の塩には、岩塩よりも多くのマイクロプラスチックが入っているのではないか?」のように、自分なりの予想(仮説)を立ててみよう。
- サンプルを準備する
- 食塩・砂糖の場合 綺麗なビーカーにサンプルを入れ、ホコリが入らないように沸騰させたお湯(または蒸留水)を注いで溶かします。
- 砂の場合 少量の砂をビーカーに入れ、水を加えてよく混ぜ、しばらく置いて砂が沈むのを待ちます。
- ろ過する サンプルを溶かした水や、砂を混ぜた水の上澄みを、ろ紙を使ってゆっくりとこします。マイクロプラスチックがあれば、ろ紙の上に残るはずです。
- 観察する ろ紙をよく乾かし、シャーレの上に置きます。顕微鏡を使って、ろ紙の表面をじっくり観察しましょう。
- 記録・スケッチ プラスチックと思われるものが見つかったら、すぐに写真を撮り、色、形、大きさをノートにスケッチします。キラキラ光るもの、いかにも人工的な色の繊維などが見つかるかもしれません。
- 考察する 観察結果から、何が分かったかを考えます。「仮説は合っていたか?」「なぜ、このような結果になったのだろか?」自分の言葉でまとめてみましょう。
自由研究から発見したアイデア
- アイデア1 減らす工夫を考えよう!
もし洗濯排水から多くの繊維が見つかったら、どうすれば減らせるでしょうか?洗濯ネットを使うと変わるかな?洗濯の頻度を減らすべき?家庭でできるマイクロプラスチック削減アクションを考えて提案してみましょう。 - アイデア2 オリジナルの調査道具を開発!
もっと効率よくマイクロプラスチックを集める方法はないでしょうか?身の回りのものを使って、自分だけの「マイクロプラスチック収集装置」を発明してみるのも面白いかもしれません。 - アイデア3 地域マップを作ろう!
近所の公園の砂、川の水、道路の隅のホコリなど、いろいろな場所からサンプルを集めて「マイクロプラスチック汚染マップ」を作ってみてはどうでしょう。どこに多いか、地域ごとの違いが見えてくるかもしれません。
この自由研究に関連する仕事
- 環境科学者・研究者 海や川、大気中のマイクロプラスチックの動きを追いかけ、生態系への影響を調査し、解決策を探る専門家です。
- 水質調査員 私たちが安全な水を飲めるように、水道水や川の水の成分を分析し、水質を管理する仕事です。
- (新素材)開発技術者 自然界で分解されやすい「生分解性プラスチック」など、環境にやさしい新しい素材を開発する仕事です。
- 環境コンサルタント 企業に対して、環境への負担が少ない製品作りや、プラスチックごみを減らすためのアドバイスをする仕事です。
まとめ
今回の自由研究は、目に見えない小さなプラスチックを通して、地球全体の大きな環境問題と繋がる、壮大なテーマです。自分の目で問題を発見し、「なぜだろう?」と考えることが、科学の第一歩であり、未来を変える力になります。この研究をきっかけに、プラスチックとの付き合い方を少しだけ見直してみませんか?君の小さな発見が、未来の地球を救う大きなアイデアに繋がっているかもしれません。
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。