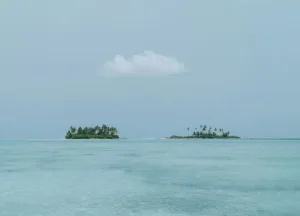教育制度の特徴
ミャンマーの教育制度は国家主導の集中管理型で、文部省(Ministry of Education)が管轄。基礎教育は5年間の初等教育(KG〜4年生)、4年間の下位中等教育(5〜8年生)、2年間の上位中等教育(9〜10年生)で構成されています。引用元neqmap.bangkok.unesco.orgWikipedia
義務教育は初等教育段階(約9歳)までとされており、国際基準の15~16歳には達していません。近年では英語教育を重視した私立校が都市部を中心に増加しています。引用元Wikipedia
教育方法
従来は暗記・講義形式が中心で、教師が一方的に知識を伝達する詰め込み型教育が主流でした。しかし、近年は生徒中心のアクティブラーニングや形成的評価を取り入れ、問題解決型・スキルベースの学習へと転換を図る政策が進められています。特に「Participatory Approach」ポリシーでは、21世紀型スキルの育成やソフトスキル向上を重視しています。引用元neqmap.bangkok.unesco.orgTaylor & Francis Online
教育への取り組みや支援
政府予算はGDPの約1.2%と限られる中、UNICEFやNGOと連携した支援が活発です。UNICEFは学習教材の提供や代替教育(Alternative Basic Education)の普及を推進し、コミュニティレベルでの学習機会を創出しています。
引用元UNICEFWikipedia
また「Bring Back Learning to Children and Adolescents」プロジェクトでは、学校再開支援や心理社会的ケアを全国展開し、学びの空白を埋める取り組みを実施しています。引用元UNICEF
さらに、10~17歳の紛争被害者向けにリテラシーやライフスキルを学ぶEXCELプログラムも展開されています。
引用元UNICEF。
子供達の1日の過ごし方
典型的な学校日は朝7時ごろ起床し、制服に着替えて8時前後に登校。朝の集会で国歌斉唱やお祈りの後、8時半~15時前後まで数学・理科・ビルマ語・英語など6~7コマの授業を受けます。昼食後は教室や校庭の清掃を行い、放課後には補習校や家庭教師を利用して追加学習を行う生徒も多く、1日の学びを充実させています。引用元Bulb
教育と社会の関係
教育は国の経済発展や社会的結束の基盤と位置づけられており、文部省は創造力や問題解決能力の育成を掲げています。引用元UNESCOデジタルライブラリ
一方で、都市部と農村部、ジェンダー間の教育格差は依然として大きく、教育権の充足度は所得水準から見ると84.3%にとどまるとHRMIが報告しています。引用元Wikipedia
これらの格差は貧困や社会的排除の要因ともなっており、教育改善は持続可能な社会の実現に直結しています。
国が抱える教育の課題と未来
主な課題は政府教育予算の不足(GDPの約1.2%)、教員数・質の不均衡、そしてCOVID-19と2021年の軍事クーデターによる公立学校の532日間におよぶ長期閉鎖など、政治的不安定による学習機会の損失です。
引用元WikipediaWorld Bank Blogs
加えて、2017年~2023年で中等教育進学率が12%以上低下し、多くの子どもが学外に取り残されています。
引用元Reuters
今後はICTを活用した遠隔教育、コミュニティ主導の代替教育、教師研修プログラム強化など多様な施策による教育再建が期待されます。引用元UNICEF
教育と文化や価値観の関係
仏教精神の継承
多くの学校では朝礼での礼拝や瞑想の時間を設け、思いやりや謙虚さを重んじる仏教的価値観を日々の学びに取り入れています。
共同作業による共同体意識
掃除や校庭の整備をクラス全員で行う「共同奉仕」の時間があり、助け合いや責任感、共同体としての一体感が自然と身につきます。
伝統芸能の学校教育
民族舞踊や太鼓演奏、織物などの伝統文化を授業やクラブ活動に組み込み、世代を超えた文化継承とアイデンティティの醸成を促しています。
祝祭行事と地域行事の連携
ティンジャン(水かけ祭り)などの行事は学校行事としても取り入れられ、地域の人々とともに行動することで地域社会との結びつきが深まります。
言語教育と多様性尊重
ビルマ語に加えて英語や少数民族の言語を学ぶ機会を設けることで、多文化理解や国際感覚、異なる背景への寛容さを育んでいます。
まとめ
ミャンマーの教育は、制度的には基礎教育を軸にした国家管理体制が整備されていますが、予算不足や政治的混乱による学習機会の喪失、都市と農村の格差など、解決すべき課題が山積しています。一方で、UNICEFやNGO、国際機関との連携による代替教育や心理社会的支援、ICT導入などの革新的な取り組みが進んでおり、未来を担う子供たちに質の高い学びを届ける動きが広がっています。制度改革と国際連携を通じて、すべての子どもに教育機会が保証される社会の実現が望まれます。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい