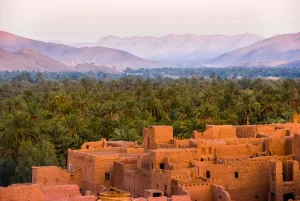教育制度の特徴
バングラデシュの教育制度は、いくつかの流れがあるのが大きな特徴です。
- 一般的な教育課程 日本と同じように、政府が管轄する一般的な学校です。小学校5年間、中学校3年間、高校2年間、大学という構成が基本です。小学校から高校(10年生)までの教科書は政府から無償で配布され、多くの子どもたちがこの課程で学んでいます。
- マドラサ(宗教学校) イスラム教の教えを中心に学ぶ学校です。一般的な科目も学びますが、アラビア語やイスラム法学などが重視されます。こちらも政府公認の課程があり、卒業すれば一般的な学校の卒業資格と同じように扱われます。
- 英語教育課程 富裕層の子どもたちが多く通う私立学校で、授業のほとんどが英語で行われます。イギリス式の教育システムを採用していることが多いです。
このように、国内に複数の教育システムが併存しているのが、バングラデシュの教育制度のユニークな点です。
教育方法
バングラデシュの多くの学校では、先生が黒板に書いたことを生徒が一斉にノートに写し、それを暗記するという、伝統的な「一斉授業」が主流です。授業は国の公用語であるベンガル語で行われます。
学年の終わりには大きな試験があり、特に小学校卒業時(PSC)、中学校卒業時(JSC)、高校卒業時(SSC、HSC)には国が定めた統一試験が行われます。この試験の結果が、次の学校に進学できるかどうかを決めるため、子どもたちは試験のために一生懸命勉強します。近年では、子どもたちが主体的に考える力を育むための新しい教育方法も少しずつ導入され始めています。
教育への取り組みや支援
バングラデシュ政府は、「すべての子どもに教育を」という目標を掲げ、様々な取り組みを行っています。
- 初等教育の無償化 公立の小学校の授業料は無料です。
- 教科書の無償配布 新学期が始まると、政府からすべての子どもたちに新しい教科書が配られます。
- 女子教育の推進 中学校に通う女の子には、政府から奨学金が支給される制度があります。これにより、かつては学校に通うことが難しかった女の子の就学率が劇的に向上しました。
また、BRAC(ブラック)のような国内の巨大NGOや、ユニセフ、日本のJICA(国際協力機構)といった国際機関も、貧しい家庭の子どもたちのための非公式教育(寺子屋のようなもの)や、先生の質を高めるための研修など、様々な支援活動を行っています。
子供達の1日の過ごし方
バングラデシュの子どもたちの過ごし方は、都市に住んでいるか、農村に住んでいるかで大きく異なります。
【都市部の子どもの一例】 朝早く起き、学校の準備をします。学校は午前中で終わることが多く、家に帰って昼食をとった後は、私設の塾(コーチングセンター)で勉強したり、友達とクリケットをして遊んだりします。
【農村部の子どもの一例】 都市部の子どもと同じように学校に行きますが、放課後は勉強だけでなく、親の仕事を手伝う子も多くいます。水汲みや薪拾い、下の兄弟の世話、畑仕事など、家庭の大切な働き手です。
残念ながら、貧困のために学校に通えず、一日中働かなければならない子どもたち(ストリートチルドレンや児童労働者)もまだ多く存在します。
教育と社会の関係
バングラデシュ社会において、教育は「より良い未来を手に入れるためのパスポート」と考えられています。
良い教育を受け、PSCやSSCといった統一試験で良い成績を収めることは、より良い大学への進学、そして安定した収入が得られる仕事(医者、エンジニア、公務員など)に就くために非常に重要です。
また、国全体の視点で見ると、教育の普及、特に女子教育の成功が、国の発展に大きく貢献しています。教育を受けた女性は、若すぎる結婚や出産を避ける傾向があり、子どもたちの健康や栄養に関する知識も持つようになります。これが、国の人口の安定や、乳幼児死亡率の低下につながっているのです。読み書きができる労働者が増えたことも、国の主要産業である縫製業の発展を支えています。
国が抱える教育の課題と未来
大きな成功を収めてきたバングラデシュの教育ですが、まだ多くの課題も抱えています。
- 教育の「質」の問題 学校に通う子どもの数は増えましたが、先生の数が足りなかったり、十分に訓練を受けていなかったりするため、授業の質が低いという問題があります。
- 高いドロップアウト率 小学校に入学しても、家の貧しさや、勉強についていけないなどの理由で、卒業するまでに学校を辞めてしまう子どもが後を絶ちません。
- 教育格差 都市の裕福な家庭の子どもと、農村の貧しい家庭の子どもとでは、受けられる教育の質に大きな差があります。
- 難民の教育 隣国ミャンマーから逃れてきた多くのロヒンギャ難民の子どもたちに、どのような教育を提供していくかという、新しく深刻な課題も抱えています。
これらの課題に対し、政府やNGOは、ICT(情報通信技術)を活用したデジタル教育の導入や、社会で即戦力となるための職業技術教育の強化などを進めています。国際社会と協力しながら、教育の質を向上させようと努力を続けているのです。
教育と文化や価値観の関係
「学歴こそが成功の鍵」という強い価値観と熾烈な競争文化
統一試験の結果が進学や就職を大きく左右するため、「良い学校に入り、良い成績を取ることが、人生の成功に直結する」という価値観が非常に強いです。このため、親は子どもの教育に莫大な投資をし、子どもたちは幼い頃から塾(コーチングセンター)に通い、深夜まで勉強します。この過酷な受験戦争は、国民的な競争文化と、学歴によって社会的地位が決まるという「学歴社会」を一層強固なものにしています。
「女性の社会進出」意識の向上と家族観の変化
政府やNGOによる女子教育の推進は、バングラデシュ社会を大きく変えました。教育を受けた女性は、経済的に自立する手段(特に縫製業など)を得て、社会における重要な担い手となっています。これにより、「女性も働き、社会に貢献できる」という意識が広まりました。また、教育を受けた女性は、早すぎる結婚を避け、計画的に子どもを持つ傾向があるため、家族のあり方や人口構成にも大きな影響を与えています。
宗教(イスラム教)と共にある生活規範
一般的な教育課程と並行して、マドラサ(イスラム神学校)が国の教育システムの一部として機能していることは、バングラデシュの大きな特徴です。多くの国民にとって、イスラム教の教えは学校で学ぶべき重要な知識であり、日々の生活の基盤となる道徳や価値観を形作っています。これにより、近代化・経済成長が進む中でも、宗教的行事や慣習が深く生活に根付いた文化が維持されています。
「暗記力」と「正解主義」を重んじる思考様式
一斉授業と暗記中心の教育方法は、「決められた正解をいかに速く正確に覚えるか」という能力を重視する傾向を生み出します。これは、権威ある人(先生や上司)の言うことを素直に受け入れる従順さや、クリエイティブな発想よりも、既存のルールや手順を堅実に守ることを得意とする国民性につながっている面があるかもしれません。
まとめ
バングラデシュは、国を挙げた取り組みと国際社会の支援により、「すべての子どもが学校に通えるようにする」という目標で大きな成果を上げてきました。特に、女の子が当たり前に学校に通えるようになったことは、国の未来を明るくする大きな希望です。
その一方で、これからは「教育の質」をいかに高めていくかという、新たなステージに進んでいます。すべての子どもが、ただ学校に通うだけでなく、そこで質の高い学びを得て、自分の夢を実現できる社会を目指して、バングラデシュの挑戦は続いています。
私たちが当たり前のように受けている教育が、世界ではまだ当たり前ではない地域もあります。バングラデシュの子どもたちの姿を通して、自分たちの環境を見つめ直し、世界が抱える問題に目を向けるきっかけにしてみてください。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい