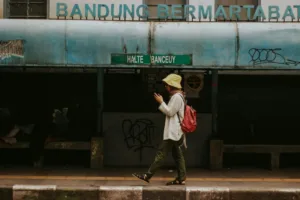今回のテーマ
「家庭で出る食品包装ごみの材質とリサイクル率調査を行い、地域ごみ分別の改善案をまとめてみよう」
この自由研究では、家庭から出る食品の包装ごみに注目します。普段何気なく捨てているお菓子の袋やトレイ、ペットボトルなどの「材質」を調査し、それらがあなたの住む地域でどのように分別され、どのくらいリサイクルされているかを調べます。さらに、調査結果を基に、地域のごみ分別のルールや方法をより良くするための具体的な改善案を考え、まとめて発表します。
自由研究の目的
私たちが毎日食べている食品の多くは、鮮度を保ち、衛生的に運ぶために必ず「包装」されています。この包装は便利な一方で、大量の「ごみ」を生み出しています。
ごみを減らす活動(Reduce)、繰り返し使う活動(Reuse)、再利用する活動(Recycle)の「3R」が重要ですが、特にリサイクル(Recycle)は、正しい分別ができて初めて成り立ちます。しかし、プラスチックごみだけでも、燃やすごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトルなど、ルールが複雑で、混乱してしまうことが少なくありません。
この研究を通じて、環境問題や資源の有限性を身近なごみを通して実感できます。そして、「どうすればみんながもっと簡単に、正しく分別できるか?」を考えることは、地域社会の課題解決能力を養うことにつながるのです。
自由研究のゴール
- レベル1 家庭で出る食品包装ごみの材質を調べ、リサイクルの種類ごとに量を記録する。地域のごみ分別のルールを正確に理解する。
- レベル2 記録したごみの量と、自治体が発表しているリサイクル率を比較し、「なぜリサイクル率が上がらないのか?」を考察する。
- レベル3 調査結果と考察を基に、地域住民がわかりやすいごみ分別の改善案(ポスターやアプリの提案など)を作成し、自治体や学校に提言する。
学校の前の歩道の調査例
私たちが普段見かける食品包装ごみには、さまざまな材質が使われています。
- ポテトチップスなどの袋 実は、見た目はプラスチックでも、「プラスチック」と「アルミ」が何層にも貼り合わされた複合素材である場合があります。このような素材は、現在のリサイクル技術では分別が難しく、燃やすごみとして処理されることが多いです。
- 卵のパック(透明) 多くはPET(ポリエチレンテレフタレート)やPS(ポリスチレン)などのプラスチックですが、地域によっては「プラスチック製容器包装」としてリサイクルできます。
- 納豆の容器やトレイ 多くはPS(ポリスチレン)で、きれいに洗えば「プラスチック製容器包装」としてリサイクルされますが、汚れが残っているとリサイクルの工程で問題になり、最終的にリサイクルされずに燃やされてしまうことがあります。
このように、「見た目は同じプラスチック」でも、材質や汚れの有無によってリサイクルの可否が変わることが、分別の難しさを生んでいます。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- ごみの分別ルールを正確に把握する あなたの住む市のごみ分別ガイドブック」や「自治体のウェブサイト」を熟読し、どの包装がどの区分(燃やす、プラスチック製容器包装、資源など)になるかを完璧に理解しましょう。
- 分別表示マークを読み解く 食品包装には必ず「プラ」や「紙」、「識別表示マーク」と呼ばれるマークがついています。これらのマークが何の材質を示しているかを理解し、見落とさないように丁寧に調べることが重要です。
- 改善案は「実現可能性」を重視する どんなに良いアイデアでも、コストがかかりすぎたり、複雑すぎたりすると採用されません。「誰でも簡単にできる」「お金があまりかからない」など、地域で実際に実行できるかどうかを考えて提案をまとめましょう。
自由研究の進め方
ステップ1 調査期間と対象を決める
- まず、ごみを調べる期間(例:1週間、10日間など)と、調査するごみの種類(例:すべての食品包装ごみ)を決めます。
ステップ2 分別と記録の準備
- ごみの種類(プラスチック製容器包装、ペットボトル、紙製容器包装など)ごとに記録用紙を用意します。
- 記録用紙には、「品目名(例:ポテトチップス)」「材質(例:プラ)」「分別区分(例:燃やすごみ)」「備考(汚れの有無など)」の項目を作ります。
ステップ3 家庭ごみの分別調査
- 調査期間中に出た食品包装ごみを、一つひとつ手に取り、分別表示マークを確認しながら、記録用紙に記入します。
- 「リサイクルに出せるごみ」と「燃やすごみになってしまうごみ」の量を数えてグラフにまとめましょう。
ステップ4 地域のリサイクル率を調査
- 自治体の環境課などに問い合わせて、「プラスチック製容器包装のリサイクル率」や「リサイクルできなかった理由(汚れなど)」を調査します。
- 私の地域で、プラスチック製容器包装は集めたうちの何パーセントが本当にリサイクルされていますか?という聞き方をすると具体的な情報を得やすくなります。
ステップ5 考察と改善案の作成
- 集めたごみの量と、自治体のリサイクル率を比べて、「どこにごみ分別の問題があるか?」を考えます。
- 例えば、「複合素材の分別が難しい」「表示マークが小さすぎて見えにくい」といった問題点から、それを解決するための改善案を具体的にまとめます。
自由研究から発見したアイデア
- アイデア1 「ごみ分別アプリ」の提案
スマートフォンで包装ごみのバーコードをスキャンすると、お住まいの地域での正しい分別方法(例:このポテトチップスの袋は「燃やすごみ」です)が瞬時に表示されるアプリを考案する。 - アイデア2 「分別体験コーナー」の提案
スーパーマーケットや公民館に、さまざまなごみのサンプルを置いて、クイズ形式で分別を学べる「分別トライアルコーナー」を設置することを提案する。 - アイデア3 「環境に優しいパッケージデザイン」の提案
分別しにくい複合素材ではなく、単一素材(例:すべて紙、すべてポリエチレンなど)で作られた包装を企業がもっと採用するように提案し、そのための新しいパッケージデザインを自分で考えてみる。
この自由研究に関連する仕事
- 環境コンサルタント 企業や自治体の環境問題(ごみ処理、エネルギー問題など)を調査し、改善策を提案する仕事。
- パッケージデザイナー・技術者 商品の包装のデザインを考える仕事。環境に配慮し、リサイクルしやすい「エコな素材」を使うための技術開発も行う。
- 自治体職員(環境部門) 地域のごみ収集や処理計画を立て、住民への分別指導やルールの策定を行う仕事。あなたの改善案が、将来この仕事で活かせるかもしれません。
- マーケティングリサーチャー 消費者の行動や意識を調査・分析し、商品やサービスの改善に役立てる仕事。ごみ分別の問題を「どうすれば消費者が動くか」という視点で分析します。
まとめ
家庭で出るごみは、資源の宝庫であると同時に、環境問題の縮図です。
この自由研究は、単に「ごみの数を数える」作業ではありません。私たちが大量生産・大量消費する社会の仕組みを見つめ直し、「どうすればもっと資源を大切にできるか?」という、未来を変えるための重要な問いに答える挑戦です。
ごみ分別を究めることは、環境への知識だけでなく、社会の課題を見つけ、論理的に解決策を提案する力を育みます。あなたの小さな調査が、地域のごみ問題を解決し、持続可能な社会の実現への大きな一歩となることを期待しています!
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。