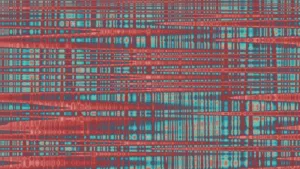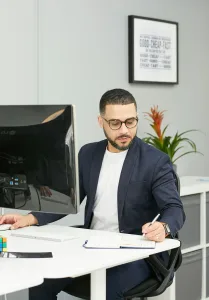モノを共有する新しい経済!シェアリングエコノミー開発者とは?
シェアリングエコノミー開発者は、使われていないモノや場所、スキルなどを、必要とする人同士で貸し借り・交換できるようにする新しいサービス(プラットフォーム)を作る仕事です。テクノロジーを使い、世界中の「もったいない」を「ありがとう」に変える経済の仕組みづくりを担います。
この仕事の最大の魅力は、社会に大きな変化を生み出す可能性を持っていることです。開発したサービスが多くの人に使われることで、資源のムダを減らし、環境に優しくなったり、人との新しいつながりが生まれたりします。例えば、使っていない部屋を旅行者に貸すことで、貸す人は収入を得られ、借りる人はホテルよりも安く、地元の人と交流できる滞在が可能です。
また、新しい発想を形にできるクリエイティブな仕事でもあります。「こんなモノが共有できたら便利なのに」というアイデアを、アプリやウェブサイトとして実現し、実際に社会で使われるのを目にできるのは大きな喜びです。人々の生活を便利にし、より持続可能な社会づくりに貢献できる、未来をつくるやりがいのある仕事だと言えるでしょう。
シェアリングエコノミー開発者とは?
シェアリングエコノミー開発者の仕事は、共有サービス(プラットフォーム)を作るためのすべてに関わります。
- サービス企画・設計 「何を、誰と、どうやって共有するか?」というアイデアを考え、アプリの使いやすさ(ユーザー体験)を設計します。
「使っていない車を必要なときだけ貸し借りできるカーシェアサービス」のルールや、予約・決済の仕組みを考えます。 - プログラミング 設計した仕組みを動かすためのアプリやウェブサイトを実際に作る作業です。
ユーザーが地図上で近くの車を見つけ、スマホで鍵の開閉ができるようにするためのコードを書きます。 - 運営と改善 サービスが安全に使われているかチェックし、利用者からの意見を聞いてより使いやすく改良し続けます。
利用者の安全のために保険の仕組みを追加したり、貸し借りの手続きを簡単にしたりします。
シェアリングエコノミー開発者の魅力!
- 社会課題の解決に貢献できる
モノを共有することで、ゴミの削減や二酸化炭素の排出量削減など、地球環境に貢献できます。例えば、電動工具をみんなで共有するサービスがあれば、一人一人が買う必要がなくなり、資源の節約になります。 - 新しい市場と雇用を生み出す
これまでお金にならなかった「空き時間」や「空きスペース」に価値を与え、新しい収入源や仕事を生み出します。 - 高い専門性と将来性
この分野は世界的に成長しており、プログラミング、データ分析、ビジネス戦略といった高度なスキルが求められます。そのため、専門家としての市場価値が高く、キャリアの選択肢が広がります。 - 平均的な年収や報酬(事例)
開発者のスキルや経験、働く会社や地域によりますが、日本のIT開発者として見ると、平均年収は比較的高く、新卒でも一般的な職種より高い水準からスタートすることが多いです。グローバル企業で成功すれば、若くして大きな報酬を得るチャンスもあります。 - 世界中の人とのつながりを創出
開発したサービスを通じて、国境を越えた人々の交流や助け合いが生まれます。あなたが作ったアプリで、海外の人が日本の文化を体験したり、災害時に助け合ったりするかもしれません。
シェアリングエコノミー開発者になるには?
- プログラミングの基礎を学ぼう!
HTML、CSS、JavaScriptなど、アプリやウェブサイト作りに使われる基本的な言葉を勉強し始めましょう。「簡単なゲームやアプリを自分で作ってみることから始められそうかな?」 - 身の回りの「もったいない」を見つけよう!
家の中や町で、「これ、誰かと共有できたらいいのに」と思うモノや場所を見つけてアイデアを書き出してみましょう。 - デザインと使いやすさを研究しよう!
人気のあるアプリやウェブサイトを実際に使って、「どうしてこれは使いやすいんだろう?」と考えてみましょう。ユーザーが迷わない画面設計を学ぶことが重要です。 - ビジネスの仕組みを理解しよう!
サービスを提供する会社が、どうやって利益を得て、運営を続けているのかを調べましょう。「無料で使っているサービスは、どこからお金が入って成り立っているんだろう?」 - 自分のアイデアを小さく形にしてみよう!
プログラミングのスキルを使って、小さなウェブサイトやアプリの試作品を作ってみましょう。実際に人に使ってもらって、意見をもらうことで大きく成長できます。
この分野で有名なプロフェッショナル
ブライアン・チェスキー氏
彼は、2007年にサンフランシスコで、家賃を払うお金がない時に、自分たちのアパートの空きスペースを貸すことを思いつきました。このアイデアを、デザイナーとしての視点とIT技術で形にし、今や世界中の旅行者が利用する巨大な宿泊シェアサービスに成長させました。彼らが始めたのは単なる「部屋貸し」ではなく、「世界中の人がどこでも地元のように暮らせる」という新しい体験の提供でした。チェスキー氏の発想と実行力は、空いている資源をどう価値に変えるかというシェアリングエコノミーの本質を示しており、世界中の起業家や開発者に大きな影響を与え続けています。
マーケィングの観点から見ると?
世界中の人口が増え、資源が限られていく中で、「必要なモノを必要な分だけ借りる・交換する」という考え方は、持続可能な社会(サステナブルな社会)を築くために不可欠です。開発者として作り出すサービスは、国境を越えて人々の生活を効率化し、例えば災害が起きた際にも、物資や場所を迅速に共有して助け合える仕組みを提供できるようになります。
また、AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といった最先端の技術と結びつくことで、車の自動運転のように「乗りたい時に、共有の車が自動で迎えに来る」といったさらに未来的なサービスも実現可能になります。この仕事は、地球規模の課題を解決し、より便利で助け合いの精神に満ちた未来のコミュニティをデザインする、最も重要な役割の一つになるでしょう。
自由研究の例
テーマ 「もし私がシェアエコサービスを作るなら?〜身近な『もったいない』を『ありがとう』に変える大作戦〜」
- 「もったいない」を発見しよう!
学校、家、近所などで、「あまり使われていないモノ」や「空いている時間、場所」を10個リストアップしてみよう。「あなたの家で、一年間に1回も使わなかったモノって何があるかな?」 - ターゲットとサービスを決める!
- リストの中から一つ選んで、「それを共有したい人(貸す人)」と「それを必要としている人(借りる人)」はどんな人か考えてみよう。
- 例: 「使っていない学習マンガ」→「お金がなくて買えない近所の小学生」
- サービスの名前とルールを考える!
サービスに魅力的な名前をつけて、貸し借りする時のルール(どうやって受け渡しするか、壊れたらどうするか、料金はいくらか)を細かく決めよう。「料金は、お金じゃなくて、別のモノ(お手伝い券など)にしたらどうだろう?」 - 設計図(ワイヤーフレーム)を作ってみる!
アプリやウェブサイトの画面を紙に書いてみよう。利用者が「探す」「予約する」「評価する」のステップを迷わず進めるように、シンプルにデザインすることがポイントです。 - 発表と考察!
考えたサービスを家族や友達に説明し、「もし本当にあったら使いたいか?」感想を聞いてみよう。このサービスが実現したら、社会はどのように良くなるか考察をまとめよう。
まとめ
シェアリングエコノミー開発者は、プログラミングの技術と、社会を良くしたいという熱い思いで、「共有」という新しい経済の仕組みを生み出す仕事です。この仕事は、私たちが当たり前だと思っている「モノを所有する」という考え方を変え、限りある資源を大切にし、人と人がつながる、より優しい未来を実現するための鍵となります。今日からあなたも、身の回りの「もったいない」に目を向け、どうすればそれが誰かの役に立つ「ありがとう」に変わるかを考えてみませんか?あなたのアイデアが、未来のスタンダードになるかもしれません!
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。