今回のテーマ
「屋外と屋内の騒音をマップ作成しよう」
私たちの身の回りには、様々な「音」があふれています。しかし、その音量が時間帯や場所によってどれほど違うのか、その原因が何なのかを真剣に考えたことはありますか?
この自由研究のテーマは、身近な場所の「音」を客観的なデータとして計測・記録し、その結果を視覚的に分かりやすい「騒音マップ」としてまとめることです。単にうるさいかどうかという感覚的な判断ではなく、音量を科学的に分析し、私たちが暮らす環境の「音の特性」を解き明かしましょう。
自由研究の目的
音は私たちの生活環境の質(Quality of Life)に深く関わっています。例えば、静かだと思っていた場所が、実は深夜に車の音で騒がしくなっているかもしれません。逆に、賑やかな場所でも、特定の時間帯は静かになる発見があるかもしれません。
この研究を通じて、あなたは以下の重要なスキルを身につけることができます。まず、科学的思考力。「うるさい」という感覚的なものを、「デシベル(dB)」という客観的なデータに変換し、原因を分析する能力が身につきます。次に、データ分析力。収集した多数のデータ(音量、時間、場所、原因)を整理し、グラフや地図として分かりやすく表現する能力が磨かれます。最後に、環境への意識。私たちの行動(車の運転、話し声、家電の使用など)が、周囲の音環境にどのような影響を与えているかを深く理解する意識が生まれるでしょう。この自由研究は、環境問題や都市計画といった、社会的なテーマにもつながる学びを与えてくれます。
自由研究のゴール
- レベル1 自宅の部屋とリビング、近所の公園など、3ヶ所の音量を、朝・昼・夜の3回計測し、グラフにまとめることです。
- レベル2 複数の場所(屋内と屋外を合わせて5ヶ所以上)で、1時間ごとに計測を行い、音量の平均値と最大値を記録します。データから、音量のピークとなる原因を詳細に分析しましょう。
- レベル3 計測データを地図に落とし込み、「騒音マップ」を作成してください。さらに、音量が高かった場所の原因について、具体的な改善アイデアや解決策を提案することに挑戦しましょう。例えば、壁の素材や交通量規制など、具体的な提案ができると素晴らしいです。
時間帯で激変する図書館の音の例
音量が時間帯で激変する場所の事例として、「図書館の周辺」が挙げられます。
- 昼間(開館時間) 図書館内は静かですが、周辺は通学・通勤の人の声や車の音で、平均50dB〜60dB程度になることがあります。
- 夕方(下校時間) 周辺の小学校や中学校から帰宅する生徒たちの声で、瞬間的に70dBを超える騒音が発生することがあります。
- 深夜(閉館後) 周辺の交通量が減り、音量が40dB以下にまで低下し、日中とは全く違う静かな環境に変わります。
このように、同じ場所でも音の主役が時間帯で入れ替わる様子をデータで捉えることが、この研究の面白い点です。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- 計測アプリの選定と統一 スマートフォン用の騒音計アプリ(Sound Level Meterなど)を使用し、必ず同じアプリ、同じスマートフォンで計測することで、データの信頼性を保ちましょう。
- 計測条件の統一 計測する際には、マイクの位置(例:床から1.2m)や計測時間(例:1回あたり1分間)を毎回統一することが重要です。
- 原因の明確な記録 音量を記録するだけでなく、その音の原因(車の通過、エアコンの運転、人の話し声、鳥の鳴き声など)を詳細にメモすることが、分析の鍵となります。
自由研究の進め方
研究計画を立てよう
自宅、公園、道路沿い、スーパーの店内、自分の部屋など、5ヶ所以上の計測ポイントを選びます。計測する時間帯を決め(例:朝7時、昼12時、夕方6時、夜10時)、最低でも3日間継続して計測する計画を立てましょう。
データ収集と記録
以下の項目を記録する専用のノート(またはExcelなどのスプレッドシート)を作成し、計測の都度記録します。記録する項目は、日付と時間、計測場所(屋内/屋外、場所の詳細な情報)、音量(計測アプリの表示:平均dBと最大dB)、音の原因(具体的に何の音か)、そして気象条件(晴れ、雨、風の強さなど)です。
グラフとマップの作成
集めたデータを基に、視覚資料を作成します。計測場所ごとに、時間帯による音量の変化を折れ線グラフで示す「場所ごとの音量比較グラフ」を作成しましょう。さらに、Googleマップなどの地図に、計測ポイントの平均音量を色分けして表示する「騒音マップ」を作成すると、結果が一目で分かります。
分析と考察
グラフやマップから見えてきた傾向について考察します。例えば、「なぜ朝7時の音量が一番高かったのか?」、「屋外より屋内の音量が急に高くなるのはどんな時か?」といった疑問を掘り下げ、原因を分析しましょう。
自由研究から発見したアイデア
- 「サイレント・デリバリー・ルート」の提案
深夜の宅配業者の配送ルートのうち、騒音が最も低い道路を「サイレント・ルート」として指定し、地域の静穏を守るための交通計画を提案する。 - 「自動音量通知システム」の開発
スマートフォンに搭載されている騒音計機能とGPSを連動させ、自分の生活圏の騒音が一定値を超えた場合に、「休憩が必要です」といった通知を出すアプリのアイデア。 - 「静音性評価ラベル」の導入
地域の公園や住宅地に対して、時間帯ごとの平均騒音レベルに基づいた「静音性評価ラベル」を導入し、人々に静かな環境を選ぶ基準を提供する。
この自由研究に関連する仕事
- 環境コンサルタント・環境アセスメント技術者 道路や工場、空港などの建設前に、その施設が周囲の環境(水質、大気、そして騒音)に与える影響を予測・調査し、対策を提案する専門家です。
- 建築音響設計者 劇場、コンサートホール、そして一般の住宅において、外部の騒音を遮断し、室内の音響を最適な状態に保つための設計を行う専門家です。
- 都市計画家 騒音マップなどのデータを利用し、静かな住宅地と賑やかな商業地を区分けしたり、防音壁の設置計画を立てたりするなど、人々の生活しやすい都市空間を計画する仕事です。
まとめ
「屋外と屋内の騒音をマップ作成しよう」というテーマは、私たちの日々の生活を科学的に見つめ直す、非常に実用的な自由研究です。
ただ「うるさい」と感じるだけでなく、騒音の原因と音量の変化をデータとして捉えることで、私たちは客観的に環境問題を理解することができます。この研究で得られたデータと分析力は、将来、私たちがより良い社会を築いていくためのアイデアの源泉となるでしょう。さあ、騒音計アプリを手に、身近な「音の秘密」を探る旅に出かけましょう!
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。








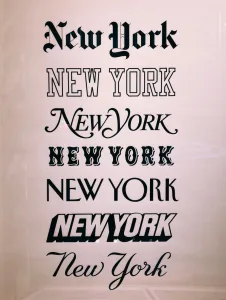

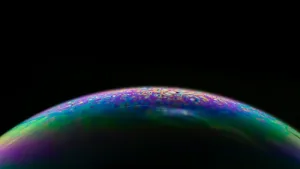





-300x300.webp)
