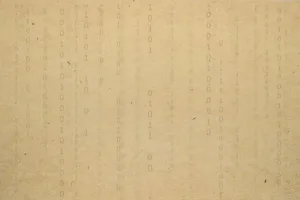楽しい公園を作ろう!みんなが遊びたくなる遊具を考えてみよう!
ブランコ、シーソー、ジャングルジム… 公園は、たくさんの遊具があって、友達と元気いっぱい遊べる、まるで夢のような場所だよね。でも最近、老朽化や安全の問題で、そうした遊具がどんどん撤去されている「公園の遊具不足」が全国で問題になっているんだ。この研究では、なぜ遊具が減っているのかを学び、どうすれば公園がもっと楽しくなるか、みんなが本当に遊びたいと思う新しい遊具のアイデアを一緒に考えていくよ!
公園は、ただ遊ぶだけの場所じゃない。思いっきり体を動かして運動能力を高めたり、友達と遊ぶ中で順番を守るなどの社会のルールを学んだり、時には新しい遊びを自分で考え出す「創造力」を育んだりする、とても大切な「学びの場」なんだ。そんな公園から遊具がなくなってしまうと、子どもたちの成長にとって大事な機会が失われてしまうかもしれない。自分たちの「遊び場」の未来を自分たちで考えることは、自分たちの成長の環境をより良くしていくための、とても重要な一歩なんだ。
自由研究のゴール
- レベル1 なぜ公園の遊具が減っているのか、その理由を知っている。
- レベル2 自分の家の周りの公園の現状を調査し、問題点を説明できる。
- レベルアップゴール 安全性や、小さい子からお年寄りまで様々な人のことを考えた上で、「こんな公園があったらいいな!」という、君だけのオリジナルな公園のプランを提案できるようになること!
この研究を通して、社会問題を自分事として捉える「当事者意識」と、新しい価値を生み出す「デザイン思考」を身につけよう!
遊具がなくなっている具体的な事例
実際に、なぜ遊具がなくなっているのか、具体的な例を見てみよう。
- 事例1 「安全」のための撤去 A公園のすべり台は、長年使われているうちに、階段の一部が錆びて少し欠けてしまった。大きな事故が起きる前に、市の職員さんが見回りに来て「このままでは危ない」と判断。修理するにはお金がかかりすぎるため、すべり台は撤去されることになった。20年以上前に作られた古い遊具は、今の厳しい安全基準に合わないことも多く、こうした例は全国で起きている。
- 事例2 「音」への苦情による撤去 B公園のブランコは、子どもたちの元気な声でいつもにぎわっていた。しかし、公園のすぐ隣に住む人から「子どもたちの声や、キーキーとこすれる音がうるさい」という苦情が市役所に寄せられた。話し合いが持たれた結果、残念ながらブランコは撤去されてしまった。
このように、安全、お金、近隣住民との関係など、様々な理由が絡み合って遊具は減っているんだ。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- 公園探偵になろう! 家の周りにあるいくつかの公園を、探偵になったつもりで観察してみよう。「どんな遊具があるか?」「遊具の数は十分か?」「遊具以外のスペースはどう使われているか?」などをメモや写真で記録する。昔の写真と比べてみるのも面白い発見があるかも!
- みんなの声を聞き出そう! 友達や兄弟、お父さんやお母さんに「どんな遊具で遊びたい?」「公園にあって嬉しいものは何?」とインタビューしてみよう。小さい子を連れたお母さんや、おじいさん、おばあさんにも話を聞くと、自分だけでは気づけなかった視点が見つかるよ。
- 世界や日本のすごい公園を調べよう! インターネットや本を使って、国内外のユニークな公園を調べてみよう。車椅子のままでも遊べる遊具がある公園(インクルーシブ公園)や、木や土、水など自然のものを活かした公園(プレーパーク)など、わくわくするようなアイデアがたくさん見つかるはずだ。
自由研究の進め方
- 調査する公園を決めよう 一番よく使う公園や、問題があると感じる公園など、テーマにする場所を一つか二つに絞ろう。
- 調査と情報収集をしよう
- 見る 決めた公園を訪れ、遊具の種類、数、状態、利用者の様子などを記録する(※必ずおうちの人と一緒に行動しよう)。
- 聞く ポイント5を参考に、インタビューやアンケートを実施する。
- 調べる 市役所のウェブサイトで公園に関する情報を見たり、図書館で公園デザインの本を探したりする。
- 分析して、課題を見つけよう 調査結果から、「この公園には〇〇が足りない」「お年寄りが休むベンチがない」など、具体的な課題をリストアップする。なぜそうなっているのか、理由も考えてみよう。
- アイデアを考え、デザインしよう 課題を解決するための、新しい遊具や公園全体のデザインを考えよう!絵に描いたり、粘土や段ボールで模型を作ったりすると、アイデアがより具体的になるよ。
- 提案としてまとめよう 「〇〇公園をもっと楽しくする提案」として、調査結果、分析、そして君の考えた新しい公園のデザインを模造紙やスケッチブックにまとめよう。なぜそのデザインにしたのか、理由もしっかり書くことが大切だ。
自由研究から発見したアイデア
- アイデア1 世代をこえる「健康バランス遊具」 子どもはアスレチックとして、大人はストレッチや簡単な筋トレ器具として使える遊具。おじいちゃんやおばあちゃんが孫と一緒に体を動かせる、一石二鳥のアイデア。
- アイデア2 自分でコースを作る「モバイル・アスレチック」 取り外しや組み替えが可能な、軽い素材でできたブロックやバーのセット。来るたびに違うコースを作れるので、創造力が無限に広がり、飽きることがない。
- アイデア3 雨の日も楽しい「屋根付きお絵かきボード」 大きな屋根の下に、水で消せる特殊なペンで自由に落書きできる巨大なボードを設置。地面が濡れていても、ここならいつでもみんなで集まれる。
- アイデア4 自然と遊ぶ「いきもの観察ステーション」 公園の木に、鳥の巣箱や昆虫ホテル(虫が冬越しするための小さな隠れ家)を設置。遊具として遊ぶだけでなく、自然や生き物の生態を学べる仕掛け。
この自由研究に関連する仕事
- ランドスケープデザイナー/造園家 公園全体のデザインを考える人。植物の知識やデザインのセンスを活かして、美しくて機能的な空間を創り出す。
- 公園遊具メーカーのデザイナー/開発者 子どもたちが安全で楽しめる、新しい遊具をデザインし、開発する仕事。
- 都市計画プランナー/公務員(公園緑地課など) 街全体の視点から、どこに公園を作るか、どんな公園が必要かを計画する仕事。住民の意見を聞くのも大切な役割。
- プレーワーカー 子どもの「やってみたい」という気持ちを尊重し、自由な遊びをサポートする専門家。「プレーパーク」などで活躍している。
まとめ
「公園の遊具が減っている」という問題は、少し寂しいニュースかもしれない。でも、見方を変えれば、それは「自分たちの手でもっと良い遊び場を創り出すチャンス」でもあるんだ。この研究を通して、君たちが「もっとこうだったらいいのに」と考え、絵や言葉で表現することは、未来の公園を作る大きな力になります。君の考えた最高のアイデアが、いつか本当の公園になる日を夢見て、まずは身近な公園をじっくり観察することから始めてみよう!
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。












-300x300.webp)