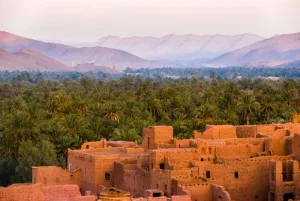教育制度の特徴
マーシャル諸島の教育制度は、アメリカの影響を強く受けており、小学校が8年間、高校が4年間の「8-4制」が基本です。8年間の小学校教育が義務教育となっており、子どもたちはみんな学校に通います。学校には、国が運営する公立学校と、教会などが運営する私立学校があります。授業で使われる言葉も特徴的です。公用語であるマーシャル語と英語の両方が使われ、特に低学年ではマーシャル語で基礎を学び、学年が上がるにつれて英語で学ぶ授業が増えていきます。子どもたちは、自分たちの文化の言葉と、世界とつながるための言葉の両方を大切に学んでいるのです。
教育方法
マーシャル諸島の教育では、一般的な算数や理科、国語(マーシャル語・英語)などの科目に加え、この国ならではの特別な学びがあります。それは、先祖から受け継がれてきた伝統文化の継承です。
例えば、かつて星や波の動きを読んで広大な海をカヌーで旅した伝統的な航海術や、植物の葉で編む「アミモノ」と呼ばれる美しい民芸品の作り方、島々に伝わる神話や伝説などを学びます。これらは、子どもたちが自分たちのルーツに誇りを持ち、マーシャル人としてのアイデンティティを育むための、非常に重要な授業となっています。
先生が一方的に話すだけでなく、子どもたちが実際に体験したり、グループで話し合ったりする活動も取り入れられています。
教育への取り組みや支援
マーシャル諸島政府は、国の未来は教育にかかっていると考え、とても力を入れています。特に、先生の数を増やして質を高めるための教員養成や、子どもたちが快適に学べる学校施設の整備に積極的に取り組んでいます。
しかし、国だけの力では難しいこともたくさんあります。そのため、歴史的に関係の深いアメリカや、日本、オーストラリア、台湾といった国々が、資金の援助や専門家の派遣、新しい校舎の建設などでマーシャル諸島の教育をサポートしています。
また、ユニセフ(国連児童基金)のような国際機関も、教科書や教材を提供したり、子どもたちの健康や栄養状態を改善したりする活動を通して、マーシャル諸島の子どもたちの学びを支えています。
子供達の1日の過ごし方
首都マジュロと、その他の「アウター・アイランド」と呼ばれる離島では、子どもたちの過ごし方も少し異なります。
首都マジュロでは、朝、子どもたちは徒歩や家族の車、乗り合いタクシーなどで学校に通います。学校では友達とおしゃべりしたり、バスケットボールをしたりして元気に過ごします。
一方、アウター・アイランドの子どもたちは、自然ともっと密接に関わっています。学校が終わると、海で泳いだり、魚釣りをしたり、家族の仕事(コプラ=ヤシの実を乾燥させたもの=作りなど)を手伝ったりすることも大切な日課です。夜は、満点の星空の下で家族や親戚と過ごす、穏やかな時間が流れます。
共通しているのは、放課後に教会の日曜学校や地域の活動に参加する子どもたちが多いことです。教会は、勉強を教えてもらったり、友達と集まったりする大切なコミュニティの場にもなっています。
教育と社会の関係
マーシャル諸島にとって、教育は国の未来を左右する重要な鍵です。
高校を卒業した若者たちの多くは、国内唯一の高等教育機関である**マーシャル諸島大学(College of the Marshall Islands, CMI)**に進学したり、奨学金を得てアメリカなどの海外の大学へ留学したりします。
教育を受けた若者たちは、国の運営を担う公務員になったり、学校の先生になったり、観光業や漁業といった国の主要な産業のリーダーとして活躍することが期待されています。
また、教育は気候変動という、この国が直面する最大の危機に立ち向かうためにも不可欠です。海面の上昇やサンゴ礁の白化といった問題を科学的に理解し、世界にその窮状を訴え、解決策を見つけ出すことができる人材を育てることが、社会全体の大きな目標となっています。
国が抱える教育の課題と未来
マーシャル諸島の教育は、いくつかの大きな課題に直面しています。
- 地理的な課題 国が1,200以上もの島々から成り立っているため、特にアウター・アイランドでは、先生や教科書が不足しがちです。また、島と島を結ぶ交通も限られており、質の高い教育をすべての島に届けることが非常に難しいのが現状です。
- 人材の流出 教育を受けて高い能力を身につけた若者が、より良い仕事や暮らしを求めてアメリカなど国外へ移り住んでしまう「頭脳流出」も深刻な問題です。
- 気候変動の影響 海面が上昇し、高潮や洪水によって学校の校庭や校舎が水浸しになる被害が頻繁に起きています。学校自体の存続が危ぶまれているのです。
しかし、マーシャル諸島の人々は未来を諦めていません。ICT(情報通信技術)を活用した遠隔授業で離島の教育格差をなくそうとしたり、国際社会と協力して気候変動に強い学校を建設したりする取り組みを進めています。自分たちの文化に誇りを持ち、地球規模の課題に立ち向かう「レジリエント(しなやかで強い)」な子どもたちを育てることが、この国の教育の未来像です。
教育と文化や価値観の関係
共有と相互扶助の価値観 「ジャムル(Jāmur)」の文化
マーシャル社会では、個人よりも家族やコミュニティ全体を大切にする価値観が教育を通じて教えられます。これを象徴するのが「ジャムル(お仕事や助け合い)」という文化です。例えば、誰かが家を建てる、カヌーを修理する、冠婚葬祭の準備をするといった時には、親戚や近所の人々が当たり前のように集まって無償で手伝います。これは、家庭や教会での「助け合いは当然」という教えが深く根付いているからです。困った時はお互い様という強い絆が、この助け合いの文化を支えています。
自然への畏敬と知識の尊重 「ウォレップ(Wōlej)」伝統航海術の継承
学校や長老からの口伝えで、星の位置、波や風のパターン、鳥の飛び方などを読んで大海原を航海する伝統航海術「ウォレップ」を学びます。この教育は、単なる技術指導ではありません。自然は支配するものではなく、対話し、敬意を払うべき存在であるという価値観を育みます。自然のサインを正確に読み解く知識を持つ者は社会で深く尊敬されます。この教育が、自然と共生し、その恵みに感謝するという文化を今に伝えているのです。
家族の絆と母系社会の文化 土地と物語の継承
マーシャル諸島は、土地や財産が母から娘へと受け継がれる「母系社会」です。子どもたちは、母親や祖母から、自分たちの土地がどのようにつながり、誰から受け継がれてきたのかという物語を聞かされながら育ちます。学校の歴史の授業だけでなく、家庭でのこの口承教育が、自分のルーツと家族の系譜への誇りを育みます。これが、個人の成功よりも一族の繁栄を重んじ、強い連帯感を持つマーシャルならではの文化につながっています。
まとめ
太平洋に浮かぶサンゴの国、マーシャル諸島。そこで暮らす子どもたちは、美しい自然と豊かな伝統文化に囲まれながら、未来を切り拓くための学びを続けています。
地理的な制約や、国全体を脅かす気候変動という大きな困難に直面しながらも、政府や地域社会、そして国際社会が一体となって、子どもたちの教育を支えようと奮闘しています。
マーシャル諸島の教育について知ることは、遠い国の話ではありません。地球環境の変化が、人々の暮らしや学びにどう影響するのかを考えるきっかけになります。この自由研究を通じて、私たちと同じ地球に暮らすマーシャル諸島の人々の生活に思いを馳せ、世界とのつながりを感じてみてください。
感想を温めよう!
- 世界の教育の内容を通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。
If you would like to publish your experience in our media, please contact us at the email address below, we publish for $300 per article.
mailto: hello@s-labo.earth
foodots.
空庭のテーマ
感想窓口
マーケティングを学ぼう!
あわせて読みたい
あわせて読みたい