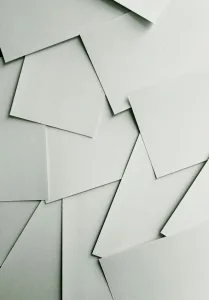食品をムダにしないために!家庭でできる食品ロス対策を考えてみよう!
食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。日本では、年間約523万トン(2021年度推計値)もの食品ロスが発生しており、これは国民一人ひとりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと同じくらいの量になります。
食品ロスは、大きく分けて2種類あります。スーパーやレストランなど事業活動から出る「事業系食品ロス」と、それぞれの家庭から出る「家庭系食品ロス」です。驚くことに、このうち約半数の244万トンが、私たちの家庭から出ているのです。
食べ残し、皮のむきすぎなどの調理くず、賞味期限切れで手つかずのまま捨てられる食品など、その原因は様々です。この研究では、まず自分たちの家庭からどれくらいの食品ロスが出ているのかを調べ、なぜそれが発生するのかを考えていきます。
食品ロスを学ぶことは、私たちの未来にとって非常に重要ないくつかの理由があります。
- 環境問題とのつながり 捨てられた食品を燃やすためには多くのエネルギーが必要で、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)を排出します。また、食品を生産するためには、水や土地、労働力など多くの資源が使われており、食品を捨てることはそれらの資源も無駄にしていることになるのです。
- 経済的な損失 食べ物を捨てることは、食費を無駄にしているのと同じです。農林水産省の調査によると、4人家族の場合、食品ロスによって年間約6万円も損をしているという試算もあります。
- 世界とのつながり 世界には、十分に食べ物がなく栄養不足に苦しんでいる人々がたくさんいます。私たちが食べ物を無駄にしている一方で、食料を必要としている人がいるという世界の食料の不均衡について考えるきっかけにもなります。
食品ロスについて学ぶことは、環境を守り、家計を助け、そして世界中の人々のことを思いやる心を育むことにつながるのです。
自由研究のゴール
- レベル1 発見力と思考力のアップ!
- 自分の家庭の食品ロスの現状を調査し、記録することで、問題を発見する力を養います。
- なぜ食品ロスが出てしまうのか、その原因を深く考えることで、論理的な思考力を身につけます。
- レベル2 計画力と実践力のアップ!
- 発見した原因に対して、「どうすれば減らせるか?」という具体的な対策を計画します。
- 計画した対策を家族と協力して実行し、やり遂げる力を身につけます。
- レベル3 発信力と提案力のアップ!
- 研究の結果や自分の考えをレポートや新聞にまとめ、人に分かりやすく伝える力を養います。
- さらに食品ロスを減らすための新しいアイデアを考え、社会に向けて提案する力を育みます。
この研究は、ただ調べるだけでなく、実際に行動を起こし、その結果から新たな学びを得るという、生きた学びの連続です。
取り組める具体的な例
家庭でできる食品ロス対策は、実はたくさんあります。ここでは、すぐに取り組める具体的なアイデアをいくつか紹介します。
買い物での工夫 「てまえどり」を実践しよう!
- スーパーで商品棚の手前にある、販売期限が近い商品から積極的に選ぶ「てまえどり」。これはお店の食品ロス削減に貢献できる簡単なアクションです。
- 買い物に行く前に冷蔵庫の中をチェックし、必要なものだけを買うようにリストを作るのも効果的です。
保存の工夫 野菜を長持ちさせる「ひと手間」
- 野菜はそれぞれに適した保存方法があります。例えば、ほうれん草や小松菜は濡れた新聞紙に包んでポリ袋に入れ、立てて保存すると長持ちします。
- 使いきれない野菜や肉は、早めに下処理をして冷凍保存するのも良い方法です。
調理の工夫 野菜の皮や芯も「おいしく変身」!
- ニンジンの皮はきんぴらに、大根の皮は漬物に、ブロッコリーの芯はスープに入れるなど、今まで捨てていた部分も立派な食材になります。新しいレシピに挑戦してみましょう。
食べ残しを減らす工夫
- 家族が食べきれる量を考えて調理する。
- 大皿で取り分けるのではなく、一人ひとりのお皿に盛り付けるようにすると、食べ残しが減る傾向があります。
- 残ってしまった料理は、翌日リメイクして別の料理に変身させる(例:カレー → カレーうどん、肉じゃが → コロッケ)。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
この自由研究を成功させるための重要なポイントは、「記録」と「比較」です。
- 現状把握(Before) まず、対策を始める前に、1週間、自分の家から出る食品ロスを記録してみましょう。「いつ」「何を」「どれくらいの量」「なぜ捨てたのか」をノートに書き出します。できれば、重さを測ったり、写真を撮ったりすると、より分かりやすい記録になります。これが最初のデータ(Before)です。
- 原因分析 記録したデータを見ながら、「なぜ食べ残してしまったんだろう?」「どうしてこの食材は使いきれなかったんだろう?」と、家族で話し合ってみましょう。原因が見えてくれば、対策も立てやすくなります。
- 対策の実践: 原因に合わせて、セクション4で紹介したような対策の中から、自分たちの家庭でできそうなものを選んで実践します。新しいルールを家族で決めるのも良いでしょう。
- 効果測定(After) 対策を1週間続けた後、もう一度、同じように食品ロスの量を記録します。最初のデータ(Before)と、対策後のデータ(After)を比較することで、自分たちの取り組みにどれくらいの効果があったのかが目に見えて分かります。
この「Before→After」の比較が、研究の説得力を高める重要な鍵となります。
自由研究の進め方
【ステップ1】計画を立てよう
- 研究の目的とゴールを決める。
- 家族に研究への協力を依頼し、役割分担を決める。
- 調査期間(例:対策前1週間、対策後1週間)と記録方法を決める。
- 記録用のノートや計量器(キッチンスケール)を準備する。
【ステップ2】調査と実践
- 現状調査(Before)
毎日、家庭から出る食品ロス(食べ残し、調理くず、期限切れ食品など)の種類、量(重さ)、捨てた理由を記録する。写真も撮っておこう。 - 分析と対策会議
- 前半の調査結果をもとに、家族で食品ロスが出てしまう原因を話し合う。
- 「わが家の食品ロス削減ルール」を決める。(例:「毎週水曜日は冷蔵庫お掃除デーにする」「野菜の皮も料理に使う」など)
- 対策の実践と調査(After)
決めたルールを守りながら生活し、同じように食品ロスの記録をとる。
【ステップ3】まとめよう
- BeforeとAfterのデータを比較し、どんな変化があったかをグラフや表にまとめる。
- 研究を通して分かったこと、感じたこと、家族の変化などを文章にまとめる。
- セクション7~9の内容を参考に、研究の結論と今後の目標を書く。
- 模造紙やスケッチブックに見やすくまとめて、完成!
自由研究から発見したアイデア
自由研究を進める中で、きっとたくさんの発見があったはずです。その発見をもとに、さらに一歩進んだ新しいアイデアを考えてみましょう。
- アイデア1 わが家だけの「もったいないレシピ集」を作ろう!
研究中に挑戦した、野菜の皮や芯を使ったリメイク料理のレシピを写真付きでまとめます。家族のお気に入りをランキング形式にしても面白いかもしれません。このレシピ集をクラスの友達に紹介すれば、みんなの家の食品ロス削減にもつながります。
- アイデア2 「食品ロス削減カレンダー」を考案しよう!
「月曜日はお肉の日」「水曜日は冷蔵庫チェックの日」「金曜日は残り物リメイクの日」など、曜日ごとにテーマを決めて、食品を無駄なく使い切るためのカレンダーを作成します。イラストをたくさん描いて、家族みんなが楽しく取り組めるように工夫してみましょう。
- アイデア3 地域を巻き込む「フードドライブ」を企画しよう!
家庭で余っている未開封の食品を集めて、フードバンクなどの団体に寄付する「フードドライブ」という活動があります。まずは自分の家から始め、慣れてきたら、マンションの掲示板や地域の回覧板で呼びかけてみるなど、活動の輪を広げていくことも考えられます。
この自由研究に関連する仕事
- 食品メーカーの商品開発者 野菜の可食部を増やしたり、賞味期限を延長したりする技術を研究し、食品ロスを減らす新しい商品を開発する仕事です。
- 自治体の職員(環境政策課など) 地域のごみを減らすための計画を立て、住民に食品ロス削減を呼びかけるキャンペーンなどを企画・実行する仕事です。
- NPO・NGOのスタッフ フードバンクやフードパントリーを運営し、企業や家庭から寄付された食品を、必要としている人々に届ける活動をしています。
- 料理研究家・管理栄養士 食材を無駄なく使い切るレシピを考案し、メディアや料理教室を通じて多くの人に広める仕事です。
- IT企業のエンジニア 食品の需要と供給を予測するAIシステムや、余剰食品を抱える店と消費者をつなぐマッチングアプリなどを開発する仕事です。
まとめ
今回の自由研究を通して、私たちは家庭から出る食品ロスの現状を知り、その原因を探り、具体的な対策を実践しました。
例えば調査の結果、わが家では特に野菜の使い残しと、ご飯の食べ残しが多いことが分り、対策として「週に一度、野菜使い切りスープを作る日」を設けたところ、野菜の廃棄量を〇〇グラム減らすことができました。
この研究で学んだ「食べ物を大切にする心」を忘れずに、これからも家族と協力して食品ロスを減らす生活を続けていきたいです。また、今後はスーパーの「てまえどり」を積極的に行ったり、地域のフードドライブに参加したりするなど、家の外でも食品ロス削減につながる行動をしていきたいです。
たった一つの家庭の小さな取り組みでも、それが積み重なれば、地球全体の大きな課題解決につながっていきます。この自由研究が、みなさんの未来の食生活を豊かにする、素晴らしい一歩となることを願っています。
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。