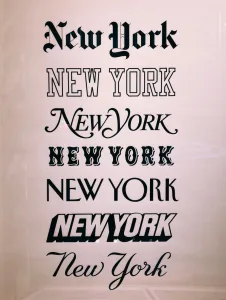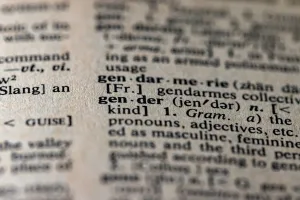CO2を減らすためにできること!省エネ生活を考えてみよう!
私たちの地球は今、「地球温暖化」という問題を抱えています。その大きな原因が、ものを燃やしたり、電気を使ったりするときに出る「温室効果ガス」、特に二酸化炭素(CO2)です。このガスが増えすぎると、まるで地球が毛布を何枚もかぶったように熱がこもり、気温がどんどん上がってしまいます。
この自由研究では、私たちの毎日の生活と地球の未来がどう繋がっているのかを探ります。「なんだか難しそう…」と感じるかもしれませんが、大丈夫!「省エネ生活」という、お家でできる身近なチャレンジを通して、地球のために何ができるのかを一緒に考えていきましょう。
では、なぜ温室効果ガスについて学ぶ必要があるのでしょうか?
それは、地球温暖化が進むと、私たちの暮らしにさまざまな影響が出るからです。例えば、夏の猛暑がもっと厳しくなったり、台風が巨大化して大きな被害をもたらしたり、北極や南極の氷が溶けて海の水位が上がり、低い土地が沈んでしまう可能性もあります。また、動物や植物がこれまで住んでいた場所で生きていけなくなるなど、自然環境も大きく変わってしまいます。
この問題は、遠い未来の話ではありません。今を生きる私たち、そしてこれから大人になる君たちの未来を守るために、温暖化の仕組みを知り、対策を考えることがとても大切なのです。「自分一人が頑張っても…」なんてことはありません。君の小さな行動が、地球の未来を変える大きな一歩になります。
自由研究のゴール
- レベル1 我が家のCO2排出量を調べてみよう! まずは、自分の家からどれくらいのCO2が出ているのかを計算して、「現状」を把握することからスタート!電気やガスの検針票(使用量のお知らせ)が調査のカギになります。
- レベル2 省エネ生活でCO2を減らしてみよう! 「使わない電気は消す」「お風呂は続けて入る」など、家族で省エネルールを決めて1週間実践!省エネ生活をする前と後で、どれだけCO2を減らせたか記録して比べ、その効果を確かめます。
- レベル3 オリジナルの省エネ活動を提案しよう! 研究でわかったことをもとに、家族や友達、さらには地域の人にも協力してもらえるような、新しい省エネのアイデアを考えて提案します。君が、地域の「エコリーダー」になるのです!
お家でできる省エネ行動の例
「省エネって、具体的に何をすればいいの?」そんな君のために、お家でできる省エネ行動の例を紹介します。
電気の省エネ
- 誰もいない部屋の照明はこまめに消す。
- テレビを見ていないときは主電源からオフにする(待機電力の節約)。
- エアコンの設定温度を夏は1℃高く、冬は1℃低くする。
- 冷蔵庫の扉を開けている時間を短くし、ものを詰め込みすぎない。
ガス・水道の省エネ
- 家族がお風呂に入るときは、なるべく時間を空けないで続けて入る。
- 料理をするときは鍋に蓋をして、火力を効率よく使う。
- シャワーの時間を1分短くする。
- 歯磨きや手洗いのときに、水を出しっぱなしにしない。
ごみ・移動の省エネ
- ペットボトルや牛乳パックなどをきちんとリサイクルに出す。
- 食べ残しをしない(食品ロスを減らす)。
- 近くの場所へ行くときは、車ではなく徒歩や自転車を選ぶ。
これらの行動一つひとつが、CO2削減につながる大切なアクションです。
研究を進めるうえで、以下のポイントに注目しよう!
- しっかり計画を立てよう 「いつからいつまで調べるか」「どんな省エネに挑戦するか」「誰に協力してもらうか」など、最初の計画が肝心です。カレンダーに計画を書き込んでみましょう。
- 記録は正確に残そう 電気やガスのメーターの数字、実践した省エネ行動、気づいたことなどをノートにしっかり記録しましょう。メーターの写真を毎日撮っておくと、間違いがなくて便利です。
- 「前」と「後」を比べよう 自由研究で大切なのは「比較」です。省エネ生活をする「前」の1週間と、「後」の1週間で、電気やガスの使用量がどう変わったかを比べることで、君の頑張りが数字で見えてきます。
- 楽しむ工夫をしよう 家族で「省エネ係」を決めたり、削減できたCO2の量をポイントにして競ったり、ゲーム感覚で取り組むと楽しく続けられます。まとめのレポートには、絵やグラフをたくさん使って、カラフルに仕上げましょう。
自由研究の進め方
ステップ1 準備と事前学習
- 地球温暖化やCO2について、図書館の本や環境省のウェブサイト「こども環境白書」などで調べてみよう。
- お家の人と一緒に、電気とガスのメーターの場所と数字の読み方を確認しよう。過去数ヶ月分の検針票も探しておくと、比較に役立つよ。
ステップ2 計画
- 「4.具体的な事例」を参考に、我が家で取り組む省エネ目標を3つほど決めよう。
- 「普段通りの生活の1週間」と「省エネ生活の1週間」、それぞれの記録期間を決めよう。
ステップ3 実践と記録
- 計画に沿って、まずは「普段通り」の生活のデータを記録。毎日決まった時間にメーターの数値をチェックして、ノートに書き込もう。
- 次の週は、いよいよ「省エネ生活」にチャレンジ!決めた目標を意識しながら生活し、同じようにデータを記録しよう。大変だったことや、家族の感想もメモしておくと、まとめの材料になるよ。
ステップ4 分析とまとめ
- 集めたデータをグラフにしてみよう。棒グラフにすると、使用量の変化が一目で分かっておすすめです。
- なぜCO2が減ったのか、または思うように減らなかったのか、その原因を考えてみよう(考察)。
- 研究の動機、方法、結果、考察、そして感想や今後の目標などを、画用紙やスケッチブックにレポートとしてまとめよう。
ステップ5 発表
- 完成した自由研究を、家族や学校の先生、友達に発表しよう。「こんな工夫をしたんだよ!」「これだけCO2を減らせたよ!」と自分の言葉で伝えることで、君の研究の価値がさらに高まります。
自由研究から発見したアイデア
この研究を通して、君だけの新しいアイデアが生まれるかもしれません。ここでは、さらに研究を発展させるためのアイデアを提案します。
- 「我が家だけのオリジナル省エネルール」を作ろう! 研究で効果があった省エネ行動や、家族みんなが「これなら続けられるね」と納得したことをもとに、家族みんなで守る新しいルールを作ってみましょう。ポスターにしてリビングに貼るのも良いアイデアです。
- 「ノーデバイス・チャレンジデー」をやってみよう! テレビ、スマートフォン、ゲーム機などを使わない日を週に一度作ると、どれだけ電気使用量が減るか実験してみましょう。代わりにボードゲームをしたり、本を読んだり、家族の会話も増えるかもしれません。
- 「食品ロス調査隊」を結成しよう! 一週間、家で出た生ごみの重さを毎日計ってみましょう。どうすれば食べ残しや、使わずに捨ててしまう食材を減らせるか、家族で作戦会議を開いて、次の週にチャレンジ!ごみを減らすことも、CO2削減につながります。
この自由研究に関連する仕事
- 環境コンサルタント 会社や市役所などに、「どうすればもっと環境に優しくなれるか」をアドバイスする専門家。
- 再生可能エネルギー技術者 太陽光や風力、地熱など、CO2を出さないクリーンなエネルギーを作り出すための技術や機械を開発するエンジニア。
- サステナビリティ担当者 企業の中で、自社の製品や活動が、環境や社会に与える影響を考え、より良くしていくための計画を立てる仕事。
- 環境省の職員(国家公務員) 日本全体の環境を守るため、法律やルールを作ったり、国民に環境保護を呼びかけたりする仕事。
- エコな製品の開発者 省エネ性能の高いエアコンや冷蔵庫、リサイクル素材を使った服など、環境に優しい商品を生み出すメーカーの社員。
まとめ
「省エネ生活」をテーマにした自由研究は、地球温暖化という大きな問題を、自分の生活と結びつけて考える絶好の機会です。毎日のメーターのチェックや記録は少し大変かもしれませんが、その頑張りが「CO2をこれだけ減らせた!」という目に見える成果になった時の達成感は、きっと格別なものになるでしょう。
この研究で得られる知識や経験は、地球の未来を考えるきっかけになるだけでなく、電気代の節約など、家計にも嬉しいおまけがついてきます。まずは「使わない電気を一つ消す」ことから。君のその小さな一歩が、自分と地球の未来を明るく照らす、大きな力になるはずです。
関連書籍
身近な仕事について考えてみよう!
- 仕事のことを通じて学んだこと、楽しかったこと、難しかったことを書いてみましょう。
- テーマについての新しい発見や、自分が感じたことをまとめます。
- 今後、さらに調べてみたいことや、他の人に教えたいことがあれば、それも書いてみましょう。